
名作写真とこども俳句で平和をかんがえる
2015年の今年は戦後70周年。6月23日は沖縄戦終結の日だが、「沖縄忌」という俳句の季語にもなっていることをご存知だろうか?当然ながら広島・長崎の「原爆記念日」や「終戦記念日」も季語であり、多く俳句に詠まれてきた。
今や親や教師が戦争を知らない世代となって久しく、家庭や教室で話す機会もすっかり減ってしまった。が、その一方で、小学校では3年生から国語教科書に「戦争のお話」が登場、同じく「俳句に親しもう」も3年生からの指導方針となっている。
親と子、教師と生徒が、一緒に「戦争」について学べる本がないなか、写真と俳句という“感性にうったえる”手法で、世代や経験を超えて理解できるよう工夫されたのがこの本だ。各写真にはこども向けの説明がついており、巻末には詳しい解説と大人・子供両用の年表も付いている。
写真は木村伊兵衛、土門拳、林忠彦ら8名による貴重な作品ばかりで、昭和30年代から50年代にかけてのこども達の生活が記録されている。現代のこども達が詠んだ俳句は率直さと感受性に溢れ、あわせて鑑賞することで戦争の恐ろしさと平和の尊さが浮き彫りとなり、身近な幸せがより深く実感できるのだ。
【編集担当からのおすすめ情報】
俳句は五七五で作る「世界で最も短い文学」といわれています。写真集としてのビジュアルと、こども達の作った純粋な文学とを、まずは味わい、何かを感じとってください。そして大切な誰かと一緒にこの本を手に取り、語りあっていただければ嬉しいです。
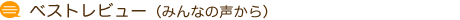
戦争と子どもたち
土門拳、木村伊兵衛、林忠彦他、そうそうたる日本の写真家たちが写した戦前、戦時中、戦後の日本と子どもたち。
先ずは写真の素晴らしさに見いってしまいました。
芸術性が高いので、悲惨さは訴えかけては来ないのですが、当時の子どもたちがどのようであったか、冷静に考えることができます。
現代の子どもたちの俳句の選択については、あえて戦争と距離感を作ったのか、不思議なコラボレーションです。
そのぶん写真に重厚感があります。
モノクロの写真を挟んだカラーの自然写真は成功とは言えませんが、平和を考えるという点で、核となる写真たちを印象づけていると思いました。
(ヒラP21さん 60代・パパ )
|