
『歌でやらかせ これくらいの仕事 生活苦にして 泣こよりも』(ゴットン節の一部)
およそ百年前。石炭増産の時代。筑豊の地底深く。力の限りに働き抜いてきた女坑夫たちの埋もれた労働と暮らしを、井手川泰子さんが記録。過酷な状況下で働き抜いた老女たちの声を二十年以上にわたり丹念に追った聞き書き―『新 火を産んだ母たち』(海鳥社・二〇二一年刊)を再構成し、待望の絵本化。若い世代へと繋いでいく。
当時の女坑夫たちが運命を受け入れた「強さ」と「軽さ」と「可能性」とは。
令和の時代を生き抜く私たちの心に、魂に今、切々と語りかけてくる。
『今のあんたたちにも、おんなじもんが残っとらんね?』(あとがきより)
『しゃんとせな。なんぼきついでも 愚痴るよか働かな どげもならん。』(本文より)
本書は、ヤマの女たちの生きた証である。
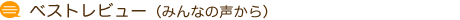
そんな時代があったことを思いました
絵本と呼ぶには少し躊躇のある「絵本」です。
さとこ虫さんの挿絵のような絵が、女鉱夫として生きてきたタカさんの肉声を、素描のように描き連ねています。
この絵本で、女性も炭坑夫として働いていた時代があったことを再認識しました。
昔の炭坑夫ですから、生身の肉体で過酷な労働条件の中を生きてきたのです。
タカさんは当てにならない夫がありました。
それに抗う代わりに、家庭では主となる働き手だったようです。
子も次々に生まれ育て、臨月でさえ炭坑に入ったというのはどんな状況でしょうか。
それでも、タカさんは前に進み続けたのです。
立ち止まったら、後を向いたら、人生に負けてしまうという、生きるための覚悟には、凄まじいものを感じます。
この境遇を肯定することはできませんが、すべてを受け止めて前へ突き進むという渾身に、生きることへの執念を感じさせられたことだけは事実です。
(ヒラP21さん 70代以上・その他の方 )
|