|
◆「声にだすことばえほん」シリーズとは?
「声にだすことばえほん」シリーズは、現在14冊出ています。
こうして並べてみると、とてもバラエティー豊かなラインナップでワクワクしてきますね。
今回は、このシリーズを担当されているほるぷ出版の編集の方にご協力頂いて、
それぞれのみどころや、楽しみ方などを教えて頂きました。
◆このシリーズをつくられるきっかけは・・・?
まず「声にだすことばえほん」シリーズがつくられる「きっかけ」というものはあったのでしょうか?
「齋藤孝先生の『声に出して読みたい日本語』をみて、これを絵本にしたら面白いのではないか、と考えたことがきっかけです。この本は大人の読者を中心に読まれていました。
でも、齋藤先生は子どもに向けて編集したものと考えられておりました。
そこで、より子どもに向けて発信できるメディアとして絵本での刊行を提案しました。」
とのことでした。また、シリーズ最初に創られたつちだのぶこさんのラフがとても素晴らしく出来上がっているのをご覧になって、もっと色々な題材が絵本になるのではないか、と考えられたそうです。
その記念すべく最初の作品がこちらです↓
ファンも多いこの作品は、レビューでご紹介しますね。
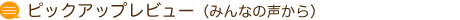
子供と一緒に声を出して楽しもう!
「声に出して読みたい日本語」の作者でお馴染みの齋藤孝さんだけに、
絵本の中に出てくる日本語は、楽しくて子供たちにも伝えておきたいものばかりです。
日本語の面白さをこんな風に、絵本にしてしまうなんて、本当に驚き桃の木山椒の木です。
お話は、おじいちゃんと、その孫である子供たちが、忍者ごっこをしながら繰り出す楽しい言葉遊びです。
あまりにもよくできていて、恐れ入谷の鬼子母神です。
こんなおじいちゃんがいたら、毎日言葉遊びから日本語が楽しく身に付いていいですね。
我が家でも、早速、声に出して子供たちと練習しています。
早く、お茶の子さいさい河童の屁で、この言葉を使いこなせるように、ただいま特訓中です。
子供たちにも大受けのこの絵本、是非続編も出るよう期待したいですね。
それまで、さよなら三角またきて四角。
(
はなしんさん 30代・ママ 千葉県市川市 女5歳、男3歳 )
◆絵本にする際に選ばれる題材には、どんなこだわりがあるのでしょう?
また、絵本作家さんとの組み合わせもとても興味深いですね。
「題材を選ぶ時は、リズムのよさ、言葉の面白さが一番。
それから、絵本にしたときに、場面がいきる展開をつくれるかどうかで考えていきます。」
↑まるで、最初から飯野先生が考えた言葉ようにマッチしていますね。
また「あの絵の人が、この文章に絵を描いたの!?」という意外性を感じるような
文章と絵のカップリングをする、ということも意識されているそうです。例えば・・・。
 |
←「春はあけぼの」
たんじあきこさんは「和風の絵を描く」イメージが殆どなかった所を
敢えてお願いしたそうです。
結果的に、清少納言の頭の中で風景が展開されるという、
ユニークなアイデアと、納言ちゃんのかわいさ、何より風景の美しさ
・・・という魅力たっぷりの、斬新な絵本が完成したそうです!
「古典なのに新しいすごい絵本だと思います。」(編集者談)
|
 |
←工藤ノリコさんも 「意外性」という事でこの題材を選ばれたそうなのですが、この強烈な可愛さを放つ寿限無くんを生み出してしまう辺りが、さすが!
子ども達も、楽しく覚えられそうですよね。
「寿限無 寿限無、五劫のすりきれ、海砂利水魚の、水行末・・・。」
|
 |
←どなたが絵を描かれたかわかりますか!?
かわいい子どもが描かれている「ますだくんのランドセル」等の作者武田美穂さんです。
どーんと描かれたおじさんの絵。この迫力ある雰囲気も新たな武田美穂さんワールドですね!
|
◆こんな変わった絵本もあります!

「るてえる びる もれとりり がいく。」
え・・・?何だ何だ、わからない。
「ぐう であとびん むはありんく るてえる。」
この不思議と耳をついて離れない詩は、日本を代表する詩人草野心平の作品です。
何と「蛙語」でかかれた詩だという。意識を持ってしまった蛙「ごびらっふ」の心境独白。
それを思いながら、声に出して読んでみる。何だか生命力にあふれているではありませんか。
そして絵をみると、幸せそうな気分も伝わってきます。
最後は、草野心平自身による日本語訳を読んで、すっと心に染み入る。
「音と絵で最初に詩を味わう」。これは、とっても面白い体験です!
(磯崎園子 絵本ナビ編集長)
↑是非、体験してみてください。
◆まだまだあります!見所を教えて頂きました。
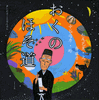 |
←芭蕉の歩いた日本各地の情景。
実際に現地まで取材に行って描かれたという美しいイラストは
眺めているだけでも楽しいのです。
|
 |
←長谷川さんの味わい深い結婚式の絵を見ているうちに、
一つ一つの早口言葉には、実は深ーい意味があるのではないか?
と思えてきます(実際には特にないです)。
これぞ絵本の力だと思います。
|
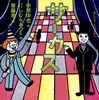 |
←一篇の詩を一冊の絵本として読むことが、すごく豊かな体験だと
感じさせてくれる絵本です。肩の力を抜いて、くりかえされる
「ゆあーん〜」という場面に酔いしれてほしいです。
|
◆この絵本シリーズの楽しみ方!
子ども達には、どんな風に楽しんでもらいたいですか?
「とにかく言葉自体の面白さ、リズムのよさなどを楽しんでほしいと思います。
シリーズの中には漢文、古文などの意味をとるのが難しいものや、文章自体に文学史的ないわれのあるもの、それからことわざ、四字熟語などの「学習」的な雰囲気の強
いものなどもあるのですが、それに対し「覚えよう」「意味を考えよう」などとかたく考えずに、文と絵の面白さを、まず楽しんでほしいです。」
最後にこのシリーズを通して、メッセージがございましたらお願いします!
「この絵本のよさは、『文学』や『国語』という舞台で取り上げられると、どうしても小難しく考えられてしまう色々な言葉を、絵本として読むことで、(文学上の位置づけや、言葉の意味などを、ほとんど気にせずに)気楽に親しむことができるところだと思います。
大人の方々も、このシリーズの『春はあけぼの』や『吾輩は猫である』を一度開いてみてください。
学生の頃に学んだときにはもしかして感じなかったような、文章の美しさ、リズムのよさなど言葉としての面白さを純粋に感じることができると思います。
(担当編集者である、私が実際に、そう感じました)。」
各絵本の最後には、齋藤孝先生が題材となった文章について、じっくりと解説してくれています。
(口語訳も記されています。)
とても読み応えがあると同時に、楽しみ方を教えてくれるので更に日本語の世界を広げてくれます。
子どもから大人まで、本当に長く愛用できそうな絵本ですね。
◆今後の刊行予定は・・・?
今後、、まだまだ続々と新しい絵本が出される予定があるそうです!
ちらっとご紹介しますと・・・。
来年春頃には長野ヒデ子さんで『外郎売り』が登場予定。
その後も、新進気鋭の作家陣竹内通雅さんやかわかみたかこさんなどなど・・・。
楽しみですね。
|


![]() All Rights Reserved.
All Rights Reserved.