|

着物姿で舞台にあがって、話術で人をたのしませる、日本の伝統芸能。
史実を元にした物語で、後世に歴史を伝える、落語とは似て非なるしゃべりの芸術。
それが『講談』!
100年ぶりの講談ブームといわれる昨今、絵本でさらに親しみやすくなった、講談絵本が誕生しました!
誰もが知っている天下の剣豪、宮本武蔵。
これは、かの有名な巌流島の戦いより以前、宮本武蔵が旅路でのひと幕……
旅の途中、妙な虚無僧に難癖をつけられ、それと立ち会うこととなった武蔵。
木剣の二刀で構える武蔵に対する虚無僧の武器は、尺八に隠した鎖鎌!
なんと虚無僧その正体は、鎖鎌の名人として名高い武芸者、山田真龍軒(しんりゅうけん)だったのです!
あまりの鎖さばきに、さしもの武蔵も追いつめられて、気づけば背後は崖っぷち!
そしてついに、山田真龍軒の鎖が武蔵の木剣をからめとった——
著者は「黒魔女さんが通る‼︎」シリーズや『世界の果ての魔女学校』で知られる、児童文学作家の石崎洋司さん。
そしてイラストは、「ねぎぼうずのあさたろう」シリーズ、『みずくみに』などの絵本作家、飯野和好さん。
独特の渋い味わいのイラストが、武蔵のチャンバラ活劇の空気感を大迫力で描き出しています。
すっ、とはらったようなまなざしに薄い唇、黒く太い眉のスマートな武蔵像もカッコイイ!
「この絵本を通じて、一人でも多くの子どもたちに講談を知ってもらえることを願っています」
とは、本書監修で講談ブーム火付け役の天才講談師、6代目神田伯山(神田松之丞)さん。
言葉のとおり本シリーズは、イラストの力でより親しみやすくなっているのはもちろん、聴き慣れない言葉も漢字と振り仮名で読むことができ、わかりやすく講談の魅力を味わえます。
巻末には、物語の舞台や登場人物について解説されていて、演目の背景を知ることができるのがうれしいポイントです。
本作を読んだあとは、きっと講談の世界をのぞいてみたくなっているはず。
(堀井拓馬 小説家)

人気沸騰中、「チケットの取れない講談師」神田松之丞さんを監修に迎えた
「講談えほん」シリーズ!
「講談」とは、古くからの日本の伝統芸能です。講談師が、実在の人物や史実とされている事象を、脚色を交えて聴く人を楽しませつつ、一人語りで読んでいきます。日本の歴史の物語を次世代につなぐために、とても大事で、いま注目されている芸能です。このたび、次世代に伝えたい講談のお話を、絵本にして子どもたちに残すために、「講談えほんシリーズ」をつくりました。
いま、飛ぶ鳥を落とす勢いの講談師・神田松之丞氏を監修者に迎え、話題を呼ぶこと請け合いのシリーズが誕生します!
人気講談師・神田松之丞さん監修による講談社創業110周年記念企画。
剣豪・武蔵と鎖鎌の名手・山田真龍軒によって繰り広げられる決闘の迫力を、
子どもたちから絶大な支持を集める児童文学作家の石崎洋司氏が文章を、大人気シリーズ「ねぎぼうずのあさたろう」や「くろずみ小太郎旅日記」でおなじみの飯野和好氏が作画を担当した声に出して読みたい絵本です。
講談の物語の魅力を存分に味わってください!
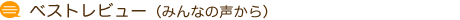
5年生への読み聞かせ
読み聞かせといえば、周りはママさんばかり。
絵本に紙芝居、たまにどでかい絵本など。
これは、男性なりのちょっと変わった読み聞かせができたらイイなぁと一考していました。
伯山さんの講談は好きで、よくYoutubeで見たり、独演会に行ったりするほど。
よく見ていた山田真龍軒の講談えほんがあると知り、
購入→特訓開始。
張扇も手作りし、伯山さんの動画を見ながらの試行錯誤。
その上で、読み聞かせをしました。
講談はもちろんほぼ全ての児童は知らないので、
・落語、講談の違いを簡単に。
・簡単なクイズ(二刀流で日本一の剣豪といえばなど)
(宮本武蔵自体を知らない児童の多さに驚き。)
そして山田真龍軒の読み聞かせの流れに。
絵本を片手に持ち、児童に見せながら、もう片手で張扇という、
かなりのやりにくさに悪戦苦闘しながらも、なんとか完読。
最後は拍手の渦に包まれて、嬉しい気持ちでいっぱいになりました。
ぜひ、興味ある方はやられた方がいい、読み聞かせにオススメな一冊です。
ただし、伯山さんの動画をそのまま覚えると、
絵本の文章との違いに戸惑いますので、ほどほどの練習に。
(ノビさん 40代・パパ 男の子17歳、男の子13歳、男の子11歳)
|