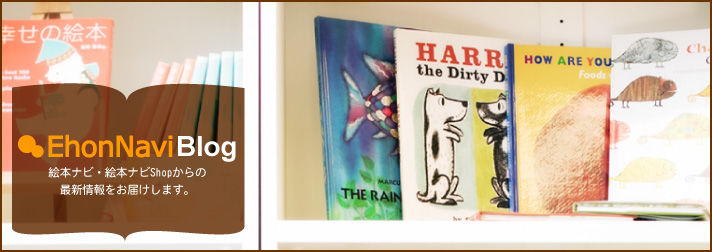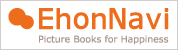絵本『きょうのそらはどんなそら』
作者のふくだとしおさんにインタビューしました!

新刊『きょうのそらはどんなそら』の発売を記念して、ふくだとしおさんが絵本ナビにいらしてくださいました!今回は今までの作品とちょっと雰囲気が違うような・・・その辺りも含めてたっぷりお話を伺いました。
この取材が行われたのは8月の終わり。思いのほか日焼けをされているふくだとしおさんの登場です。聞けばこの夏は1歳8ヶ月(取材当時)になられた娘さんのベランダのプール遊びに付き合っているうちに焼けてしまった「ベランダ焼け」だそうで(笑)・・・そんな愛らしいお話などを伺いながら和やかな雰囲気でインタビューはスタートしました。
 ※みどころはこちら>>>
※みどころはこちら>>>
『きょうのそらはどんなそら』 ふくだとしお+あきこ accototo ・作 大日本図書刊
<新刊『きょうのそらはどんなそら』制作秘話>
■ 『きょうのそらはどんなそら』での初めての試み
―― とにかく色々な空が登場するこの絵本。空をテーマで絵本をつくろう、と思われたきっかけなどはあったのでしょうか?
かつて、ふくだとしおさんがご自身のHP上で、娘さんの誕生日に「その日の、各地の空の写真を送ってください」と募集されたことがあったそうです。
「日にちを告知して募集したら、本当に色々な都市や外国の空まで集まって。すごく面白かったんです。それを見た(担当編集者の)山本さんが『空の本をかきませんか?』と声をかけてくださったのが直接のきっかけですね。僕自身もともと小さい頃から空が好きだったこともあり、お話を頂いた機会にじゃあちょっとやってみたいな、と。」
目の前に『きょうのそらはどんなそら』の油絵で描かれた原画をずらっと並べてくださいました!


▲何とも深い味わいで思わず見入ってしまいます。
―― 今回の作品は今までの作品とガラッと雰囲気が変わって油絵という技法を使って描かれています。背景や空をじっくり描かれる為に素材を変えられたのかな、とも思ったのですが・・・?
「そうですね、実際に空とちゃんと向かいあってじっくり描きたい、というのはありました。」とふくださん。
「最初は油絵で描くつもりじゃなく、いつもと同じように水彩で・・・と思っていたんです。でもどんな絵本にしていこうかと話している中で『油絵はどう?』と奥さんが言い出して。油絵だったら面白いんじゃないかな、と思えてきたんです。より空の雰囲気や奥深さが出るんじゃないか、と。
同じタッチじゃなくてもいい、という話をもらっていたこともあって描いてみることにしました。
油絵というと、今までも自分では描いてはいたのですが、絵本で使うのは初めてだったんです。
でもずっと水彩で描いてきていて、ちょっと慣れてきちゃっているなあ、という思いもあって。画材を変えることで完成図がみえなくなる、そういう状態で描ける面白さの方に惹かれました。自分自身が楽しめるんじゃないか、と。」
―― そうして新境地に進まれる事を選んだふくださん、今回は更に原画のサイズを決めないで描かれたそうなのです。
「キャンパスのサイズは決めないでください、と申し出たんです。とにかく自由に楽しく描きたいから、と。後はデザイナーさんに調節してもらって(笑)。
というのも、以前ジョン・バーニンガムの原画展を見に行った時にびっくりしたんです。実際の絵本と原画が全然サイズが違ったり、同じ原画なのに、サイズが全然違ったり、切り取って貼っていたり・・・もうむちゃなくちゃなくらい。
でも、絵を描く側の目から見たらそんな風なのが自由で楽しいなぁと感じていたんですよね。だから一度(原画のサイズを決めないで描くということを)ちょっとやってみたいと前から思っていたんです。」

―― 実際描かれてみてどうでしたか?
「油絵を絵本にするということは、水彩と違って上から塗り重ねたりできるのでより自由に絵を変えられるんですよね。だから僕自身の気持ちは結構楽でした。大きさのこともあって、硬くならずにより自由に描けたような気がします。
こういう広い空を描く時に、表現がちまちまならずに良かったなぁ、と思ってます。」
―― 結構時間がかかったのでは?
「いや、結構早いですよ。乾く時間を考えなかったら一日一枚描けちゃうくらい。もともと描くのは早い方なんですけどね。
制作中に立ち止まってしまった、といったことはなかったです。全部の絵を同時に進めて描いていくんです。それを引き出しに入れておいて、それぞれに手を入れたり、また並べてみて眺めたり。そうやって常に全体を見ながら描き進めていきました。
原画を描く段階にくるまでは色々と変わったりしてそれなりに時間はかかったんです。描きたい空のイメージが固まるまでは何となくずっとふわふわしていて・・・。でもあるシーンが固まってからは早かったですね。」




▲アイデアを練るためのラフ。小さいサイズでも本の形になっているのです。 可愛い!
何種類ものラフが繰り返し制作されています。最初のものとはかなり違う内容になっています。
■ 主人公は子猫のプチュ
―― 実はこの絵本の主人公である子猫は既刊『ぴっちゃんぽっちゃん』で登場する子猫<プチュ>なのだそうです。だから続編とも言えますね。そんなプチュに空を見させると何とも空の大きさが際立つ様です。一日中空を見て過ごせるのもプチュだからこそ?いい生活だなぁ、なんて(笑)。最初からプチュに空を見せようと思っていたのですか?
 >※みどころはこちら>>>『ぴっちゃん ぽっちゃん』 ふくだとしお+あきこ accototo ・作 大日本図書刊
>※みどころはこちら>>>『ぴっちゃん ぽっちゃん』 ふくだとしお+あきこ accototo ・作 大日本図書刊
「そうですね。こんな風に一日を過ごすのは、いたって猫らしい行動ですよね。
僕の実家で飼っている猫も3日間帰ってこない、ということがあります。どこかで別の名前で呼ばれていたりして。だから気ままに空を見てても違和感ないと思うのです。
人間の子どもが同じようにしていたら『ごはん食べているのかな』『トイレどうしているのかな』なんて気になっちゃう様な気もしますしね(笑)。」
―― 『ぴっちゃんぽっちゃん』でプチュはとても小さな世界の中での発見を描き、今作でのプチュはとても大きな世界との出会いを描かれているような気がします。特に暮れかかった大きな空のなかにたたずむプチュの小さな姿の場面がとても印象的です。
実はラフスケッチの3番目くらいで夕日の場面というのが出てきたそうなのです。それを見て編集の山本さんが「ふくださんが描きたいのはこれじゃないかな。」と思われたそうで・・・。
「なかなか定まらなかったイメージをうまく拾って頂いた、という感じですね。そこからどんどんと広がっていきました。その後は早かったですね。」

▲見る者の胸にぐっとくる夕日の場面。プチュの小さなシルエットも何だか切ない気がして・・・。
「この夕日の場面についてはさみしい感じがするのではないか、と言う話もあったんですが、僕は子どもにとってそういう感情はとても重要だと思っているんです。
『さみしいな・・・』とか『かなしいな・・・』とか、そういう深刻ではない位の軽い『さみしさ』や『かなしさ』みたいなもの。或いは夕日をみて切ないと感じたり。今から振り返ってみると、そういう感情ってすごく豊かな気がするんですよね。そういう切ないなぁという感情を子ども達にも大切にして欲しいと思っています。
自分で改めて見ていても(この場面は)さみしい気がします。でもこういうのもいいんじゃないかなぁと思ってます。」
■ 記憶の中の空を探して・・・
―― 夕日の場面の切なさと合わせて、この絵本に描かれている風景というのも特に知っている訳ではないけれどとっても懐かしい感じがします。
「僕は小さかった頃、団地に住んでいたんです。
背景として描く場所をどうしようかと、小さい頃に住んでいた所と似たような場所を探していたところ、すごくイメージに近いところがあったんです。その辺りをぶらぶら歩いていたら、子どもの時の具体的な記憶じゃなくて<匂いのような記憶>といった感じのものがふわーとでてきて・・・。
この団地とか、この辺りを描きたいなと思ったんです。
なんかいいんですよね、団地って・・・(笑)。
大人の方が見ても、具体的な記憶をたどりながら『ちょっと懐かしいなぁ』と思ってくれるといいですよね。『あーこんな空見たことあるなぁ。』なんてゆっくり空を見てもらいたいな、というのもあるんです。」

―― この絵本のために実際に空を探しに行かれたりはなさったんですか?
「実際に空を探しに行ったり、というのはしていません。具体的にこの空というのは決めてないんです。思い出の中に残っている空の印象が強いので、逆にそれを大切にしたかった、というのがあります。一応描く為に、夕日の色や青い色などは見て参考にしてはいますけど、具体的な場面というのではなく、今見ているものと自分の記憶を合わせながら描いていくという作業でしたね。ほとんど想像です。
雲のかたちもイメージなんです。(表紙にも登場するもこもこ雲とか)実際にはあんな雲はないとは思うけど、自分の子どもの時には本当に実際にあったような気もしたりして。それは自分が作り出しているだけなのか、本当なのかどうかはわからないけど、イメージの中には確かに残っているんですよね。
風景にしても団地があって、フェンスがあって、工場が遠くにあって・・・こういうのも記憶の一場面なんですよね。」
■ 最終的に完成するまでに
―― そんな風にイメージが固定していってから、更に完成するまでにはちょっとだけ苦労されたそうで・・・。
「今回文章はちょっと悩んだかもしれませんね。
テキストは随分変わりました。最後にはかなり削ったりもしています。最終的に決定するまで、ちょっと違うなというのがずっとあって・・・。じっくり考えるというのではなくて、自分の心を広げて余裕をもたせた上で考えたいなと思ったんです。
そこで・・・旅行へいこう、と。
僕が好きな沖縄の小さな島へ一泊しに行きました。昼過ぎに着いて、夕方空を見てボーっとして旅館の部屋で文章を考えて。」
編集の山本さんがある日もらったテキストがあまりにも違っていて、それが凄く良かったのでふくださんに尋ねたら「旅行に行ってきました。」と答えられたそうなんです(笑)。
「真摯に空と向かいあってみたいなあと思い、家の中ではなく、ちょっと外に出て自然に言葉が浮かんでくるような状態、環境をつくったんです。」
結果的に読んでいる人の想像力や懐かしい記憶を喚起させるような、とてもシンプルな文章が出来上がったのです。
―― 作家ふくだとしお+あきこ accototoとして、奥様のあきこさんといつもお二人で制作されているそうですが、今回でいうと具体的にどんな作業分担になったのでしょうか?
「通常はストーリーは二人で考え、色づくりは奥さんです。『あたたかさを感じる茶色』といったふうに、イメージを伝えます。今回は自分の記憶を呼び起こしてながら一気に表現したかったので、この作品に関しては色も含めて僕が主体となって制作しました。奥さんは、構想とか絵本全体のながれを考えたりとか、今回は一編集者的な役割りでしたね。」
■ 子どもの頃に見た空の記憶は宝物。
―― この作品をこんな風に楽しんで欲しい、というのはありますか?
「今の子どもたちを見ていると、(ゲームをやっていたりして)ちょっと目線が下向きの様な気がするんです。もっと空を見てほしいなと思いますね。空って本当に毎日違いますよね。勿論似たような空もあるんですけど、厳密にいったらやっぱり絶対違う。
僕自身が子どもの時、あるきっかけがあって『ああ、空好きだな』と思ってから結構空を見るようになったんです。近くにあったマンションの一番高い所に登っては、兄とお小遣いを出しあって買ったカメラでしょっちゅう空を撮っていました。その12階でいつも撮っているうちに、そこに住むおばさんとも知り合いになって『今日はどう?』なんて聞かれたりしてね。そんな会話ですごく仲良くなったりもしました。ライフワークみたいになっていましたね。それって本当に豊かだったなぁと思うんです。
言葉では何も語らないけど、空は語ってくれるんです。嫌なことがあったら空を見て、より悲しくなる場合もあれば、そこから回復することもあったり・・・。幼いながらに空と向き合っていて。例えばきれいな夕方を見れば早く写真を撮りに行きたいなぁと思ったり、元旦だけは兄と分かれてそれぞれ朝日を撮って見せ合ったり。そんな興味を毎日自然に感じていました。
子どもも大人も、もっと空と向かい合って欲しい、そこかららもっと感じて欲しいなぁと思いますね。」
―― お話しを伺っているだけでもソワソワしてきます。何だか毎日空を見ていないのが損した気分!?になってきたりして。
「例えば子どもが凄いものを発見したかのようにキラキラした目で『おかあさん、雲が動いているよ!』なんて言ったりしますよね。子どもにとっては大発見です。親は流さないで一緒に付き合ってほしいですよね。
また大人になると当たり前になっている事でも、時間を巻き戻して子どもの気持ちになってみるとそれはすごい感動するっていうことは沢山あると思うのです。そういう薄れていく感動というのを大切にして欲しいな、と思います。」

「子ども達だけでなく、お母さんやお父さんにもこの絵本を一緒に見て欲しいですね。これをきっかけに空を見ながら色々話したりしてくれたらこの作品を描いて良かったなと思えます。」
■ ご自身について伺いました。
―― 『うしろにいるのだあれ』を始めふくださんの作品は「ひとりじゃないよ」と、とても大きくて温かい愛情を伝えてくれていると思うのですが、最近ではもっと具体的なテーマ、例えば『みんなにこにこ』の様にお友達との関わりだったり、心の変化が描かれていたりする気がします。お子様が誕生されて、制作にも変化がうまれたのでしょうか?
「子どもにあたえる、という気持ちは強くなった気がします。例えば食べものでも安心感のあるもの、からだにいいものをと考えるように、描く側としてはやっぱりからだにいいもの、心にいいものをあげたいなと思いますね。
今までは作品のダミーを机の上で声に出して読む程度だったのですが、今は子どもを膝に乗せて読んでみたり。反応が見られるので、実験ではないけれどそういう役割りを担ってもらってはいますね。
言葉の重要性、音としての言葉、リズム感、そういうものを以前よりも意識するようになったかもしれません。色に関しても発見が多いですね。絵を並べて描く事が多いのですが、子どもが反応するかなと思って塗った色がそうでもなかったり。明るい色にぱっと反応するけど、じっと見ているのは意外と暗い色だったりするんですよね。
大人が思う『子どもはこうだ』という枠みたいなものは、実は存在していないのではという事がわかってきたんです。子どもはもっと広い範囲でものを感じているんですよね。
だから、もっと僕自身は自由に描けたらいいなと思うようになりました。子どもが誕生して、自分の世界を広げてもらったような感じがするんです。」
―― ふくださんのアトリエはリビングと仕事場が隣合わせ、そして奥様も一緒にお仕事をされるので境界がないそうです。それはとっても大変な事ですけど、家族にとってはとても密な時間、そして作家としてもとても影響を受ける事は多いのでしょうね。
「子どもには仕事って言う感覚がないので、わたしにも描かせろ!と言わんばかりにクレヨンを持ってきて描こうとしたり(笑)。」
やっぱり大変!?

―― 絵本作家になられて一番よかったな、たのしいなと思われる瞬間はどんな時ですか?
「絵本をつくる、それ自体がすごく楽しいです。だから、それが今できているという事が嬉しいですよね。仕事っていう感覚があまりなくて、好き勝手に絵本がつくっていられて、それが仕事になっている・・・という感じ。もちろん、制作している際には迷ったり悩んだりという事があって、それは言い換えると苦しいという事になるかもしれない。でも、僕はそれも含めて楽しいと感じます。わからないからいいのであって、逆にゴールが見えていて、それに向かって作っていくのは何だか面白くないと思うのです。ああでもない、こうでもないと言いながら出来上がったものを後で見て、その過程も含めて楽しいなと。
原画が出来上がっちゃうと、もういいや、次の作品!ってなってしまいます。そういう意味ではちょっと無責任かもしれませんね(笑)。」
―― ずっと絵はお好きだったんですか?
「そうですね。もともと絵は好きで、その頃から感覚は変わってないですね。一枚の絵と、文章を含めた何枚かの絵のつながりで表現するという違いはありますけど、基本的にはあまり変わってないです。一枚の絵の良さもあるけど、絵本というのは絵を何枚も連ねて展開していって一つの作品にします。表現の幅が出ますよね。その作業自体が面白くて自分自身が楽しんでいるんだと思います。」
―― 今後こういう絵本が描きたい、というのはありますか?
「次にこういう絵本が描きたいな・・・と思って描き留めているノートは結構たまっています。だからアイデアはたくさんありますね。今後こんな絵本をつくっていきたい!というよりは、その時その時自分の中で出てくるものを、ちょっと時間をおいて熟成してみて、いいものになりそうかなと思ったら出していきたいな、と思っています。
絵本を通して何かを具体的に強く伝えたいというわけではなく、また面白ければ何も伝わらなくてもいいと思っている訳でもないんです。大切なものがちょっとあればいいかな、と。具体的に言葉でいう場合もあるけど、そうじゃなくて空気みたいなもので語れたら一番いいなと思ってます。
子どもは言葉じゃないところで通じ合えるところがあると思うので、(今回の本も)そういうものが伝わればいいですね。」
■ 最後に・・・
――絵本ナビ読者の方へメッセージをお願いします!
「子どもと絵本を読む時、はっきりいっちゃえば僕はどんな絵本を選んでもいいと思うんです。
親子で読んでいる雰囲気が一番大切です。
親がぎすぎすしていたり、忙しそうにめんどくさいなと思って読んでいるのは例えどんないい絵本でもよくないと思うんです。あまりいい本じゃなくても、親がその子にすごく楽しませたいなとか、読んであげたいなと思うと、多分それは子どもに伝わると思うんですよね。
絵本というのを親子の楽しい時間をつくる道具として使ってもらえればそれだけで充分です。
親も余裕を持って絵本を読む時間というのを本当に大切にしてもらいたいですね。絵本を読んでいるというだけじゃなく、違うコミュニケーションが存在していると思っています。」
ありがとうございました!
制作について話される時と、お子様について話される時と同じくらい楽しそうな優しい笑顔がとても印象的なふくださんなのでした。

絵本制作は全てが楽しくて仕方がないとおっしゃるふくださんですが、それはもしかしたら新しい事に立ち向かう時の答えが見えない時の不安や悩み、それさえも楽しんでしまえる大らかな心と才能の持ち主だから出てくる言葉なのかもしれません。改めて天性の絵本作家さんなのかもしれないなぁと感じてしまうのでした。
きっと子育てに対しても同じ姿勢で取り組まれているに違いありません。
今後も御本人の中の好奇心がなくならない限り、ずっと私達を楽しませてくれる作品を生み出されていくのだろうという確信がもてて、何だか嬉しくなりました。
★絵本ナビ読者の方へ向けて素敵な直筆メッセージを描いてくださいました!
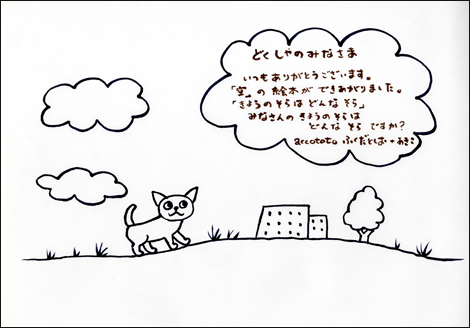
accototo ふくだとしお+あきこ さんの作品はこちらから>>>
accototo ふくだとしお+あきこ さんのHPはこちら>>>