
山の奥深くにある家で仲よく暮らす、にこにこ、ふくふく顔の10人のおふくさんたち。
誰もが笑顔になってしまう絵本、『おふくさん』。日本の心が大切に描かれ、縁起物が散りばめられた、福いっぱいのおめでたい絵本でもあります。お正月や節分の時期にぴったりの一冊。家族みんなで読んで笑って、1年の福を呼び込みたいですね。
この絵本がどのように生まれたのか、どんな思いがこめられているのか、作者の服部美法さんにお話を伺いました。みんなを幸せにする「おふくさん」のヒミツが明らかに…? どうぞお楽しみください!

───おふくさんたちのふくふくの笑顔に、絵本を開くたびとても幸せな気持ちになります。
まず、この絵本が出版された経緯を教えていただけますか?
編集担当の當田さんに、別の絵本のラフを見てもらっていたのですが、まとめあげるのにちょっと苦労をしていました。そのとき「この絵本はちょっと眠らせておいて、違う絵本も考えてみては?」と提案されたんです。「そうだなあ」と思って、それまでに描いていたいろいろな絵を見てもらったところ、「百福図(ももふくず)」というタイトルの、おふくさんを100人描いた絵が、世界観があって良いので、絵本にしてみてはということになりました。
「百福図」を描いているときは、絵本にとは考えていなかったのですが、「絵本にしてみては」と言われて考えだしたら、絵本の『おふくさん』ができあがりました。
───おふくさんが100人! 「百福図」というタイトルも、とてもおめでたいですね。
三重県四日市にある「山画廊」で個展をしたときに、出品した作品です。
もともと「百福図」というのは、古くからいろいろな画家が描き、招福の絵柄として人気を得ていたものです。私は、春夏秋冬の4つの画面にそれぞれ25人ずつ、合わせて100人という「百福図」を描きました。4枚の絵柄は繋がって1枚の絵になります。1年中、おふくさんたちのように にこにこ、ふくふく くらせますように…と願いをこめたものです。



服部さんの描いた「百福図」
───「百福図」の絵にも鬼がいて、おふくさんと遊んでいますね! 四季折々の風景の中で楽しそうに遊ぶおふくさんたち。このままおはなしの一場面のようです。
『おふくさん』の絵本のテーマも、この絵を描いたときのまま。「百福図」の絵を描いたときの気持ちをストーリーにしていきました。
───絵のテーマがおはなしとして完成するまでに、編集者さんとどんなやり取りがあったのでしょうか?
最初、おはなしに登場する鬼は、赤鬼、青鬼、黄鬼と3人でした。
當田さんと話し合う中で「言いたいことを絞って、極力、シンプルに!」と言われ、作りこんでいくうちに、鬼は3人いるよりも1人の方が分かりやすい…となり、赤鬼だけになりました。
───10人というおふくさんの人数も、編集者さんとのやり取りの中で決まったのですか?
當田さんと話していて、子どもが数えやすい人数、10人にしました。一方、おふくさんたちの名前は、日本の季節感を出したくて、「睦月」、「如月」など陰暦の月の名前にしました。
───10人のおふくさんたちに対して、月の名前は12ありますね。

見返しでおふくさんたちの名前とキャラクターが紹介されています!
「みなづきさん」と「ながつきさん」がいないのは、読者に自由に想像してもらったら楽しいかな? と考えました。どこかの家に「福」をもたらしに出かけていて留守とか、お嫁に行っちゃったとか…(笑)。
───想像が広がりますね。おふくさんたち、それぞれが魅力的で、ページごとに一人ずつ追って見るのも楽しいです。くいしんぼうの「はづきさん」、お世話好きな「うづきさん」などなど…。キャラクター設定はどのようにされたのでしょうか。
「おふくさん」の絵本を作ることになって、改めて自分の周りに目を向けると「おふくさん」みたいな人がたくさんいることに気がつきました。何でも笑い飛ばして「わっはっは〜」という母をはじめ、家族、友人など、それぞれにモデルがいます。
その中の1人は、テレビで偶然知った、いじめっ子を笑わせることでいじめを克服したという森三中の大島美幸さんです。大島さんには『おふくさん』が出版になったとき、1冊お送りしました。ちょうど息子さんが産まれたタイミングで、しかも息子さんの名前が「笑福(えふ)」君。ぴったりだと思いました。
───どのおふくさんも生き生きしているのは、モデルになった方の笑顔が宿っているからなんですね。どのおふくさんが自分や周囲の人に似ているか、探してみるのも楽しそうです。服部さんご自身は、どのおふくさんが1番好きですか?
どのおふくさんも好きで、誰か1人を選ぶことはできません。自分自身は、くよくよするタイプなので、どのおふくさんも「こうなりたいな〜」という理想ですね。



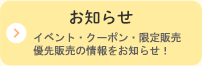











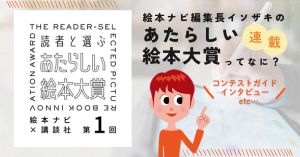
 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪ 
