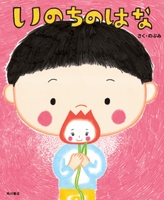●「読み聞かせ」と「朗読」「ナレーション」の違いとは?
のぶみ:実は今日、窪田さんにお会いできることになって、ぜひ聞いてみたいことがあったんです。ぼくは絵本作家になってから、講演会などで絵本の読み聞かせをすることが多いんです。最近『いのちのはな』のような大人が感動してくれる絵本を描くようになって、自分自身でどうやってお客さんの前で絵本を読んだらいいのか、すごく考えるようになりました。
窪田:ぼくもそのことをのぶみさんに聞いてみたいと思っていたんですよ。ぼくがナレーションをするときは、出来上がった映像があって、そこに流れる音楽があって、言葉を乗せていくんです。そこにお客さんの反応はありません。でも、大勢の前で行う絵本の読み聞かせは、すぐそこにお客さんの反応があるわけじゃないですか。読み聞かせをするときは、どんなことを考えていて、何に注目しているんですか?
のぶみ:読んでいるときは、聞いてくれている人の反応が知りたいので、子どもたちの顔を観察したり、笑いが起こったところを覚えていたり、五感をフル稼働させて、お客さんの反応を感じています。

窪田:それはすごく神経を使いそうですね。
のぶみ:はい。でも、より良い作品にするためには、とても大切な作業です。ぼくが窪田さんに聞いてみたかったのは、別のインタビューで「ナレーションをしているときは、自分が前に出ないようにしている」と答えていることがあって、それはどういう意味なのかと、ずっと気になっていたんです。
窪田:「情熱大陸」の場合、主役は画面に取り上げられている人だから、ぼくは目立ちすぎないように、かといって引きすぎないように、テレビを見ている人に、主役のことを分かりやすく伝えることに徹しています。
のぶみ:そういうときは、頭の中にその人のことを思い浮かべたりするんですか?
窪田:ナレーションを入れるときは、もう映像も音楽も出来上がっているので、それを見て声を乗せていくイメージですね。頭の中に情景を思い浮かべて言葉にするのは、朗読のときだと思います。朗読は、書かれている文章を全部一度、映像として思い浮かべないと、ぼくの場合は声に乗せることはできませんね。
のぶみ:ぼくも読み聞かせをするとき、登場人物の気持ちになって、感情をこめて読むことが多いです。そうすると、聞いている人たちもグッと作品の中に入ってきてくれるような気がするんです。窪田さんは「情熱大陸」のナレーションをするとき、あまり感情的にならずに、かといって、抑えすぎることもなくとても自然体で声を出しているように思いました。
窪田:そうですね。映像を見て、文章を読んで、そこで発した感情を素直に声に乗せるようにしています。ぼくが大切にしているのは「間」ですね。
のぶみ:「間」?
窪田:たとえば、「ついに、彼女の思いが叶った」という文章があったとします。文章では、区切りなどはありません。でも、ぼくは「ついに彼女の思いが……叶った」」と間を取って言いたいと思うんです。
のぶみ:その「間」には、何が込められているんですか?
窪田:「思い」です。それと「やさしさ」のような感情かな。でも、読むときは「間」をあけても、気持ちは止ぎらせないようにします。その「間」は「。」ではなく「、」なので、気持ちはつながっているんですよ。
のぶみ:ぼくは大勢の前で読み聞かせをするときに、目の前の子どもに読むべきか、大勢に届くように読むべきか、いつも悩んでしまいます。「情熱大陸」はそれこそ何万、何十万人という人が聞いている番組だと思うのですが、ナレーションをするときは、どのくらいの人に向けて声を出しているイメージですか?
窪田:「情熱大陸」の場合は、音楽や題材、そこに乗せる文章によって変わってきます。スポーツの場面だと、遠くに届けるようなイメージで声に躍動感を出すようにしますし、バーのような静かな空間の場面では、すぐそばにいる人に語り掛けるように話す。ラジオ番組などのときは、マイクのすぐ先にいる人に向けて、声を出しています。先ほどののぶみさんの話ですが、講演会のときは、目の前の人に語り掛けたり、遠くにいる人に向かって、呼びかけてみたり、いろいろやってみるのがいいんじゃないでしょうか?
のぶみ:遠くの人に向かって話すときは、大きな声を出すことが多いですか?
窪田:どの言葉をどう伝えたいかによって、声のトーンは変わってくると思います。ぼくらはよく言葉を「立てる」というんですが、ぼくの中でとても印象深いエピソードがあって、以前、映画監督の市川崑さんと仕事をしたんです。そのとき崑さんは「窪田さん、この文章を立ててください」と言われたんです。ぼくは言葉を強調させて、声を張って読んだんですが、あまり納得されていないようで、何度もリテイクをしました。そのとき、市川さんが教えてくれたのが、言葉を張るのではなく、他よりも小さく、ささやくように言うことで、言葉を「立てる」方法でした。それはまさに目から鱗が落ちた思いがしました。
のぶみ:ぼくも、感情を表現するとき、自分の内側に向かって、ささやくように発する方が、聞いている人に響いていると思うことがあります。

窪田:それが立て方の違いなんですよね。
のぶみ:なるほど……。すごくわかりやすいです。ほかに気を付けていることはありますか?
窪田:そうだなぁ……読み聞かせは本当にしたことがないんだけれど、あえて言うとしたら、地の文の読み方を変えてみるということかなぁ。特に『いのちのはな』は魅力的なキャラクターがたくさん出てくるから、地の文を少し落ち着いて、ゆっくり読むだけで、キャラクターの言葉が立ってくると思います。
のぶみ:キャラクターの演じ分けはどうしたら良いと思いますか?
窪田:絵本は絵があるから、キャラクターをイメージしやすいというか、映像を描きやすいと思います。例えば、バーバラーはバラだから、意地悪な言葉を発しても気品を感じさせるように読むのが良いと思いますよ。
のぶみ:なるほど! たしかに気品を出すようにして読むと、より個性が際立ちますね。
窪田:もし菊みたいな、あまり派手じゃない花なら。ちょっと声のトーンを落として読むのもいいんじゃないかな。
のぶみ:そうか……。だから、頭の中で絵を描くことが大切なんですね。
窪田:はい。あとやはり「間」と「テンポ」が大事ですね。













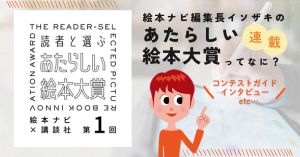
 【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット
【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット