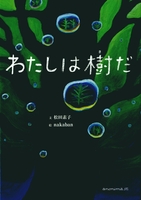●「帰省する電車で読んだ絵本が、私のターニングポイントになりました」
───絵本の帯に書かれている「はじめての ホリスティック絵本」という一文。『わたしは樹だ』を読むと、ホリスティックとはどういうものか、感覚として感じることはできるのですが、改めて、「ホリスティック」の意味を教えてもらえますか?
それは、私よりもこの絵本を企画した、アノニマ・スタジオの方から話していただいた方がいいかな……。
私も、それまでは、「ホリスティック」という言葉は意識の中にはありませんでした。でも、ホリスティックの概念を聞いたとき、それは私自身が子どものとき以来ずっともっている「つながり」への興味と同じだと思ったんですね。それと、もうひとつ。絵本というメディアは、人の心の真ん中に何かを伝えるのには、とても優れたメディアだという確信がありました。
───以前おはなしを伺ったとき、大学で宮沢賢治の作品と出会ったのと同じころに絵本と出会ったとおっしゃっていましたよね。
今でこそ、絵本の仕事をしていますが、私が絵本というものを意識したのは21才のときだったんです。それまで絵本というものを意識したことがなかった。歩いていけるところに本屋らしい本屋が一軒もないところで過ごしていましたし、いまほど情報がある時代ではなかったので、絵本を知らないで育ったと言っていいと思います。絵本に出会ったのは、東京の大学に入ってからのある夏、実家の山口県に帰省するときのことです。電車の中で読む本を持って出るのを忘れてしまって、駅前で本屋に寄ったんだけど、そのときふと、まだ入ったことがない本屋に行こうと思った。それが運命のわかれ道(笑)。店に入ったとたん「しまった」と思いました。買おうと思っていた文庫本がほとんどなくて、あせってしまった。でももう他の本屋に行く時間がない。仕方なく目の前に平積みされていた本を中身も見ないで衝動的に買ったんです。どうしてそんなことをしたのか、いまも自分でも説明できない。だって帰路は10時間もあるのに、たった32ページの本――つまり「絵本」を買ってしまったんですよ(笑)。仕方ないや、読んだら寝てようと思ってページを開きました。ところがそのとき、とんでもないことが起こった。帰路の間ずっと、そして帰ってからも、ずっと絵本のことを考えていました。世の中にこんなやり方があったのか……、こんな表現があったのか!……って。まさかそれが自分の仕事になるとは思いませんでしたが、そのとき、「私は一生、これ――絵本というものを読もう」と心に決めたんです。
───そこまで心を動かされた絵本は何という作品だったんですか?
『はせがわくんきらいや』でした。作者の長谷川集平さんと私は同い年なので、そういう意味でも衝撃が大きかった。その後、紆余曲折があって、編集者という仕事に就くことになるのですが、そんな出会い方をしたものですから、絵本というメディアには、絶対的な信頼を持っているんです。
───ホリスティックという考えも、絵本を通して多くの人に伝わると松田さんが確信している理由が分かったように思います。
20歳すぎた私自身が、一冊の絵本に、人生を左右されるほど揺さぶられた経験をしていますからね(笑)。……この絵本も、願わくば、手にした方の心の中に、なにかの種を落とす役目をになえたらと思っています。そしてゆっくりと根をのばしてくれたらと願っています。大人にも子どもにも、すべてのことが深くつながっていることを感じてもらえたら、ほんとうに嬉しいと思います。
───絵本を作っているときに、ホリスティック教育の関係者の方に感想を聞いたりしましたか?
屋久島おおぞら高等学校の生徒は、年に一度の屋久島へのスクーリング以外は、自宅から近いサポート校−KTC中央高等学院に通っているのですが、編集者さんが『わたしは樹だ』のテキストを、そこに通っている子どもたちに読ませてくれました。
───子どもたちの反応を直接知るのは、とても緊張しますね!
正直、編集者に見せるより怖かったですよ(笑)。彼らは、おべんちゃらなんか一切言わないだろうし。でも、すごく真剣に読んでいたと、反応を教えてもらってホッと安心しました。
───ホリスティック教育に触れている子どもたちにも、絵本のテーマがしっかりと伝わったんですね。

───絵本という媒体は読者の中で不思議な残り方をすることがありますよね。思い返したときに、意外なフレーズが心に残っているんだと気づくとき、本当に不思議な媒体だな……と感じます。
さっきも言いましたが、ほんとうにすごいメディアだと思いますよ。絵本を読んでいる時間は小説や他のメディアなどより短いかもしれないけど、その届き方や刻まれ方の深さは決して劣るものではない。いやむしろ、もっと深いかもしれないと思うことすらあります。
───今回、松田さんは作家として絵本に携わっていますが、編集者として携わるときと、気持ちの変化はありますか?
だぶる部分もありますが、やっぱり違いますね。著者ってこんなふうにドキドキしながら原稿を渡しているんだなあ……って思いました(笑)。編集者の必要性をあらためて感じます。
───今までも編集者として、そしてときに作者として絵本に関わられていらっしゃいますが、今後の目標というか、気持ちの変化などはありましたか?
ここ10年くらい、自分の役割とかバトンの継承みたいなことをすごく考えるようになっているのですが、『わたしは樹だ』を創る過程で、屋久島にご縁ができて、今年もう一度、屋久島に行きました。そこで出会った人たちとの会話の中で、あらためて、私は屋久島に対して何か役割があるんだろうか……という気がしてきています。そういうことを、うちの夫(※絵本作家のきたむらさとしさん)に話したら、めずらしく「あるのかもね」と共感してくれました。初めてですね。あの人がこういうことで同意してくれたのは……。たいていは「気のせいだよ」と笑われるんですけど。
───松田さんが屋久島での出会い、つながりをこれからも発信してくれることは、私たちにとってもすごく嬉しい事です。

今回のことで、とてもありがたいチャンスをもらった感じがします。私自身もゆっくりと、木の根っこが長い時間をかけて伸びていくように、まだまだいろんなことを探っていきたいと思います。
───絵本ナビでも、この絵本が生まれた奇跡のようなつながりを、多くの人に知ってもらえるよう、頑張ります。今日は本当にありがとうございました。

















 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪