●「子どもの頃、真夜中に目覚めたときの感覚、この絵本の根底に流れています」
───植田さんにとって、「おやすみ」の時間はほかの時間よりも特別な感覚でしたか?
子どものときにふと夜中に目が覚めて、眠れなくなるときが誰でも1度はあると思うんですが、ぼくにとって、それがとても印象的な一場面になっているんですよね。暗いんだけど月明かりがあって、窓の影が見えて、家族はみんな寝ているけれど、ぼくは目が覚めていて...その夜の色が「青」につながったんです。
───子どもの頃って、一度眠って次に目を開けたら朝になっている印象がありますから、夜中って未知の時間帯なんですよね。
そうなんです。しかも、夜に目覚めたときには、不思議とイマジネーションが働いて、ちょっとした物音でも想像力がどんどん広がっていくような...自分の中の想像の世界から外に飛び出していけるような、どこまでも広がっていく感覚でした。
───『おやすみのあお』で描かれている世界も、まさにそうやって色んな夜の世界が描 かれていますね。なかでも一番ハッとしたのが、一面明るい色彩に包まれる場面。私は、この明かりが日の光のようにみえて、「朝が来るという喜び」を表現されているのかな...と感じました...。

───これは、夜の月明かりなんですね!
実際には、こんなに黄色にはならないんですけど、夜にはこういう、野生のシビアな部分も、当然潜んでいると思うんです。それは、人間が知らない厳しい現実の姿です。そういう場面を指し込むことで、ぼくが描きたかった夜の時間に、さらに近づくんじゃないかと描きました。
───だから「ぼくのしらないこと」という文章が添えられているんですね。野生動物に見つめられている緊張感に、ドキッとしました。
ぼく自身としては、どう受け取っていただいても良いと思っていて、読む人にゆだねている感覚なんです。希望と取るか、緊張と取るか、空想と取るか、現実と取るか...それは、 読者ひとりひとりの状況や心境によって、その都度変わっていくものだと思っています。
───心境によって感じ方の変わる絵本...。何かあるごとにページを開いて自分の感覚と 向き合ってみたくなりますね。大人は自分なりに解釈をして、希望を持ったり、感傷に浸 ったりするけれど、子どもがどう思うかは、作者としても楽しみですよね。
そうですね。子どもがどうやって楽しんでくれるかはとても気になるところです。ただ、 ぼくも子どもを経験して、大人になって、今があるので、自分の中の子どもの部分に素直になれば、子どもたちにもきっと伝わると思っています。
───『おやすみのあお』では、文章がとても詩的に流れていく感じがしたのですが、文章を生み出す作業は大変ではありませんでしたか?
これまでとはまた違う作り方をしていたので、難しい部分は確かにありましたが、「おやすみ」に絞り、自分の個人的なところに向かうことで、いくつかの言葉がでてきました。あとは呼応するように、言葉も絵も生まれていったという感覚です。
───『おやすみのあお』というタイトルが、すごく印象的で心に残りますよね。このタイトルは最初から決まっていたのですか?
「おやすみのあお」は、描き直す前のテキストに入っていたフレーズのひとつでした。夜の青を描こうとした時にこれをタイトルにしようと思いました。でも、絵が全部描き終わるまでは決めないで、絵がそろって初めて、「これは『おやすみのあお』なんだ」 と、納得した感じです。
●デザインを担当した羽島一希さんにおはなしを伺いました!
───羽島さんは、数多くの絵本作家さんの作品のデザインを手がけてきた、絵本の世界で有名なデザイナーさんですが、今回、植田さんの作品をデザインすることになった経緯を教えてもらえますか?
植田:羽島さんはぼくが 20 代で『イラストレーション』誌「ザ・チョイス」の大賞受賞したころから、ずっと作品を観てくださっているんです。今回、ぼくの絵本で初めてデザイナーさんにお願いすることになって、編集者さんから相談を受けたときに、是非、羽島さんにお願いしたいと思い、お声がけしました。
───羽島さんが最初に植田さんの作品を観たときの印象はいかがでしたか?
とにかく、繊細の塊ですよね。
───たしかに、繊細なタッチですよね。

でも、繊細の中には“脆さ”が含まれていることがありますよね。植田さんの初期の絵ではコラージュや文字を入れることで画面を引き締めて、脆さになりそうなところをみごとにクリアしていたけれど、作品を作り続けていく中で、脆さになりそうなところを強さにどう昇華させるのかが勝負だなあと個人的には思っていました。 で、その強さを確信したのが去年、京都にあるメリーゴーランドという絵本専門店で開催した個展の絵でした。今までよりもさらに繊細な部分が際立ち、それでいて力強い。ここまで 共存できるのか!と感動しました。その絵を見ていたから、今回の絵本の仕事が来たとき は、本当にうれしかったですね。
───作家さんや編集者の仕事はなんとなく分かるのですが、デザイナーの仕事ってどんなことをしているのか、ほとんど分からなくって...。簡単にデザイナーのお仕事を教えていただけますか?
デザイナーといっても、いろんな方がいますので、一概にこうだとはいえませんが、一般的には、本の中の文章の書体や大きさ、どこに配置するか...などの位置を決めたり、表紙やカバー、帯、見返し部分などのデザインをすることです。
───作家さんが作った作品を、私たちが手に取る絵本の形に整えてくれるのが、デザイナーのお仕事なんですね。絵本のデザインを手がけるとき、デザイナーはどの段階から関わるのですか?

───原画ができあがるまでは、どんな作品ができあがるのか、ドキドキして待っている感じですね(笑)。初めて『おやすみのあお』の原画を見たときは、どう思いましたか?
京都の個展で観た絵の印象がありましたから、どんな作品ができあがるのかワクワク予想はしていました。でも、予想をはるかに上回る作品ができあがって、とても感動しました。ぼくはデザイナーであると同時に、植田真の絵のファンですから。この素晴らしい世界をなるべくそのまま、世の中にどうアピールしていくかをすごく考えました。
───やはりデザインをするときは悩んだり、緊張することもありますか?
『おやすみのあお』に関しては、一切緊張せず、原画を見せてもらった瞬間に文字を入れる位置や書体がパッと浮かんできました。
───表紙をパッと見ると、絵の美しさももちろんですが、タイトルの置き方が、オシャレだな!と思いました。それから表紙をめくると水色の見返しが来て、最後は濃い藍色の 見返しで終わっている。この色の変化にこだわりを感じました。
この絵本は「おやすみ」の時間を繰り返しているけれど、その「おやすみ」が単純に眠る前の「おやすみ」であるという感覚が、ぼくはしなかったんですね。時間も夜と限定されていないし、光も月の光なのか、日の光なのか、読者に想像の自由がゆだねられている。本当の夜じゃなくて、意識の中や空想の中の「おやすみ」かもしれない...。そういう絵本の中での時間や空間の推移は読者に委ねたうえで、一冊の絵本としての結構を示したかったので、前と後ろを違う色にすることにしました。












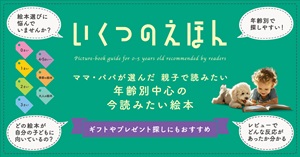
 【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット
【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット 


