●寺村輝夫さんとの出会い、堀内誠一さんとの出会い
大学を出てからデザイナーやイラストレーターとしてフリーで働いていた頃、仕事をしていたデザイン会社の方があかね書房さんに私の絵を紹介してくれたのね。そのとき、あかね書房にいたのが寺村輝夫さんだったの。寺村さんはその頃すでに編集長と作家の二足の草鞋をはいて活動していて、王さまの本も発表していたんだけど、王さまのイメージをもっと確立できる絵描きを探していて、私に声がかかったの。そのとき寺村さんが出した条件は、「3年間は、ほかの人の創作作品に絵を描かないこと」だったのよ。

寺村さんが見た和歌山さんの絵。
王さまを描くきっかけとなったとっても貴重な作品です。
───それは寺村輝夫さんの専属画家になるということですか?
───和歌山さんはアド・センターで、プロの仕事を直に体感したんですね。

───和歌山さんが『ぼくは王さま』の絵を最初に描かれたのは1967年の『王さまばんざい』からですよね。最初に王さまの文章を読んだときはどう思いましたか?
面白くて面白くて、「王さまをずっと描いていけたら良いな」と思ったわ。…まさか本当に40年以上も描き続けることになるとは思わなかったけれどね(笑)。でも同時に、王さまはすでに一流のイラストレーターの方が描いていたから、本当に私に描けるのか、不安も大きかったわ。私の絵で「王さま」シリーズを出版することを決めた当時の理論社の小宮山量平社長は「作家の世界に引きずられるのではなく、画家である和歌山さんの思うように描きなさい」って言ってくれたんだけど、最初の頃はまだ自分で描けるままにしか描けなくて……、でも今から思うとそれはそれで良かったのかもしれないの。だんだん寺村さんの言われるように描けるようになって行って……。

初期の頃の王さま。
髭や王冠などのアイテムは変わっていません。
───和歌山さん自身が、自由に王さまを描けるようになったと感じられたのはいつ頃からですか?

その頃、といっても「ちいさな王さま」シリーズの頃だから1985年くらいなんだけど、王さまの絵は、鉛筆で描いたラフを寺村さんや編集者に見てもらって、寺村さんからOKが出てはじめて、本絵を描くという手順だったの。でもあるとき…ラフのOKをもらってしまうと、いざ本絵を描くときドキドキしていない自分に気づいたのね。それで私、寺村さんに会ってラフを見せる約束の日に、全部本絵を描いて持っていったの。それを寺村さんはあっさりと受け入れてくれて…。それが、私が王さまに対して一歩前進したと自分で感じた時期じゃないかな。といっても、寺村さんは常々、作品の中に飛び込んで主人公と同じ気持ちで描かなければ作品は生まれないって言っていたから、「和歌山静子がやっと自分で気づいたか…」って思ったかもしれないわね(笑)。
●息子が生まれて変わった、絵本に対する思い。

───きっと、和歌山さんが絵描きさんだから、自然と文章に目がいったんですね。

『よあけ』
そう。特に瀬田貞二さんの訳した『よあけ』(作・絵:ユリ・シュルヴィッツ、訳:瀬田 貞二、福音館書店)を読んだとき、それを強く感じたの。瀬田さんの簡潔な訳文は、シュルヴィッツの静かな絵に本当にしっくりと合っていて、それでいて子どもにおもねっていない。「やまが くろぐろと しずもる」なんて難しい表現が使われているんだから…。でも、絵を見れば確かに「しずもる」様子が感じられるの。それ以外の表現では伝わらないと感じるくらい、ぴったりな言葉の選び方なのよね。子どもは目で絵を読んで、耳で言葉を読むんだなぁ…って。そう思えたら、絵本の絵は最初に言葉を覚える子どもにとって、すごく大事なんだ。そこに描かれている言葉をしっかりと感じられる絵じゃないといけないんだって感じたの。
───息子さんに王さまを読んだこともあるんですか?
当時、うちの本棚には、いろんな絵本がたくさんあって、ちいさな図書館みたいだったんだけど、私、王さまだけは息子に見せなかったの。だって、王さまは何十冊もあるのよ。それを「読んで!」って持ってこられたら大変じゃない(笑)。でもあるとき、王さまの原画を描いている場面を息子に見つかってしまってね。それからはちゃんと見せるようになったわ。






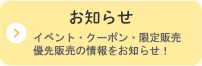







 【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット
【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット 








