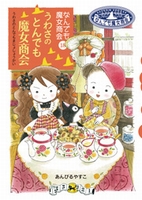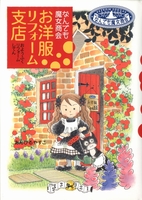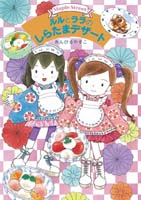●女の子モノの玩具開発の経験から、私の作品は生まれました。
───あんびるさんは絵本作家としてもたくさんの絵本を出版されていますが、「なんでも魔女商会」のような女の子をターゲットにした児童書を書こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

私は元々、着せ替え人形やキャラクター商品などの女の子向けの玩具開発会社に勤めていたんです。そのときに感じていたのが、「子どもはキャラクター商品をほしがるけれど、大人は与えたくないと思っている」という商品の矛盾点でした。でもその矛盾にずっと疑問も抱いていて、子どもも大人も喜んでくれるものがきっとあるはずだって考えたとき、私の中でそれが児童文学じゃないかと思ったんです。お母さん達は子どもに読書をしてほしいと思っている。子ども達は魔法やファッションといった大好きなものをテーマや設定に持ってくれば、きっと楽しんでくれる。子ども達の好きなものは、玩具開発時代のリサーチで培われていたので、それを惜しみなく使いました。そうして生まれたのが「なんでも魔女商会」や「ルルとララのおかしやさん」のシリーズです。
───元々キャリアのあった、絵本ではなく児童書を選ばれたのは何故ですか?
絵本はどちらかというと親が選んで与えるもの。児童書は子どもが選ぶものだと思うんです。なので子どもが選んで、親も喜んで買ってもらえるような児童書を作れたら良いなと思って、児童書の世界にチャレンジしました。
───先ほど「ルルとララのおかしやさん」シリーズの話がでましたが、あんびるさんは「なんでも魔女商会」以外にも、低学年向けの「ルルとララのおかしやさん」シリーズや高学年向けの「アンティークFUGA」シリーズも人気ですよね。
私が対象年齢の異なる3シリーズを同じペースで書いているのは、はじめ、「ルルとララのおかしやさん」から児童書を読み始めた子が、学年があがるとともに「なんでも魔女商会」、「アンティークFUGA」と高学年対象の作品に読み進めるようにという思いからです。最終的には児童書から一般書の世界に飛び立っていくまで、寄り添いたいと思っています。

───あんびる先生の作品を読むということが、その子の中では本を読む原動力になっているのかもしれませんね。
それはすごくうれしいことです。読書をする子は、1年生でも「なんでも魔女商会」を読んでいたり、小学校3年生くらいで「アンティークFUGA」を読んでいたりするんです。子ども達の読書力のすごさには驚かされます。
───「ルルとララのおかしやさん」シリーズは登場するお菓子がおいしそうなことと、包丁や火を使わずに、子ども達が失敗しないようなレシピが載っていることにとても感動しました。
「ルルとララのおかしやさん」は毎回レシピを考えるのが一番の山場で苦しいところです(笑)。女の子が料理を作るのって、自分のためよりも誰かに食べてもらいたいという思いが強いので、はじめてでも絶対に失敗しないよう実際に試作して作品にします。もちろん、おいしいこともはずせないです。
───どのシリーズもおいしいレシピが載っていますが、中でもとりわけ豪華なのが最新作『ルルとララのレシピカードブック2&パティシエノート』ですよね!

これは『わくわくクレープ』から『しらたまデザート』までのレシピと追加のオリジナルレシピが掲載されている以外にも、『ルルとララのレシピカードブック1』のレシピカードを収められる専用ケースや、ホットケーキやクッキーに絵をつけられるオリジナルステンシルシートが入っているので、本当に豪華な内容になっています。パティシエノートのデザインもとってもかわいいので、是非手にとってもらいたいですね。
───「ルルとララのおかしやさん」シリーズは特に、文字の中に小さなイラストが入っていたり、ページの番号がかわいいデザインだったりと、文字と絵のバランスが絶妙なのですが、ページの作り方などはどうやって考えているのですか?

ルルとララの制作過程を特別に見せていただきました。
下は下絵が入ったラフデザイン、上がカラーのデザインです。
一般的には、編集者が絵の入るシーンとその配置を決めるのですが、ルルとララや魔女商会では、絵と文章が互いに入り込むような形になることを目指しているので、挿絵の配置とサイズは自分で決めています。作り方としては、まず全ページ分のレイアウト(文章と絵の入る場所を指定する設計図のようなもの)を作ります。決められたページ数ぴったりにおさめるのには、いつも苦労しますね。次にレイアウト通りに文字を置いたゲラを編集に作ってもらって、そこに絵の下書きをします。そうやって、文字が入り切らなくなったり、妙な余白ができたりしないようにしているんです。
───元々、絵も文章も書かれるあんびるさんならではの方法ですね。
このようなデザインにしたのは、海外の図鑑の写真と文章がとてもバランスよく組み合わさっている感じがすごく好きで、こんな風に本を作りたいと思ったことが前提にあります。全体のデザインをしながらおはなしを作っているので、ページを見たときに面白い画面になっているなと感じてもらえたら嬉しいです。

















 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪