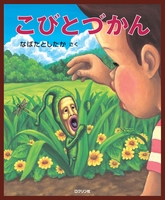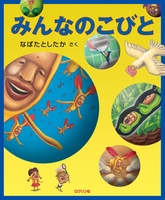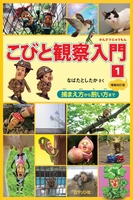●240種のコビトが大集合!『こびと大図鑑』
───最新刊『こびと大図鑑』は今までのシリーズ集大成のような、本格的な「図鑑」です。登場するコビトの数を聞いて、ビックリしたのですが……。
240種の「コビト」が登場します。
───240種! そんなにコビトを生み出されたんですね。

6か月近く、外出を控え、家にずっと引きこもってコビトを描いていました(笑)。『こびと大図鑑』は、ぼくが子どものころに大好きだった図鑑をモチーフにしています。子どものころ、絵本を読んだ記憶がほとんどないぼくですが、図鑑はボロボロになるくらい何度も何度も読みました。ぼくの子ども時代の図鑑は、ほとんどが筆で描かれた動物たちでした。今主流となっている鮮明で迫力満点の写真ではなく、今見ればかなり粗削りなイラストです。顔の表情も時には不鮮明だったりして。でもそれがとても想像を膨らませてくれていました。ぼくが夢中になっていた「図鑑」を、あえて今再現してみようと思ったんです。
───たしかに、昔の図鑑はイラストがメインでしたね。大人の方の中には、この『こびと大図鑑』の雰囲気に懐かしさを感じる人も多いと思います。
大人たちには懐かしく、子どもたちには新鮮。絵に曖昧さをもたせることで、想像力を働かせてほしい。それが『こびと大図鑑』のコンセプトです。お父さんが子どもと一緒に見ながら「パパが子どものころは、こんな図鑑がたくさんあったんだよ……」と話しをするきっかけになれたら嬉しいです。でも、「写真を使わず、全ページを絵で描く!」と宣言しておきながら、実際に240種のコビトを考えて描くのはとても大変でした。
───どうやってコビトを生み出していったのか、そのひらめきがとても気になります。
それはコビトによって違うんです。ビジュアルから思い浮かぶこともあるし、名前から出てくるときもある。例えば、カクレモモジリは、名前を思いついて、それからビジュアルや設定を固めていきました。「昔の人はどうやって桃太郎を考えたのかな……」と思って、「カクレモモジリがいたからだ!」とひらめいたときは、気持ちよかったですね。
───桃太郎“が”モデルの「カクレモモジリ」ではなくて、桃太郎“の”モデルの「カクレモモジリ」なんですよね(笑)。
そうやって考えると、昔話に出てくる主人公はみんなコビトがモデルなんじゃないかと思えてきて、タケノカグヤやカメノツキビトが生まれました。『こびと大図鑑』に出てくるコビトたちは、そうやって、ひとつ発想したら、想像力を膨らませて、どんどん連想させていって生み出していきました。

「カメノツキビト」
───特に会心の出来のコビトはいますか?
とてもひとつにしぼれませんが、カゾクグルミの習性「オシナラシ行動」を思いついたときは、すごくテンションが上がりました。

「オシナラシ行動」
───「ズットスメル」という匂いを出して、動物をおびき寄せ、巣に運ばせるんですよね。巣で動物のツボを押して、気持ちよくさせることで、巣の中にずっと居続ける「オシナラシ行動」。本当にそういう習性を持つ動物がいるんじゃないかと思うくらい、現実味のある習性だと思いました。
あと「ツチノコビトの変態」を思いついたときも「よし!」と思いました。変態するおかげでタツノエンギモノやハクジャノイワイなども生み出すことができました。

「ツチノコビト」
───『こびと大図鑑』の中には、各コビトの紹介だけでなく、どのように暮らしているか分かる絵もたくさん載っています。森の中の様子や海の中の様子の絵では、生き生きとしたコビトたちの暮らしぶりを感じることができました。でも、なかには、かなり衝撃的なページもありました……。
「ヒグマとリトルハナガシラの死闘!」ですね。これはぼくもお気に入りの絵のひとつです。

「ヒグマとリトルハナガシラの死闘!」
───『こびとづかん』のころからリトルハナガシラは凶暴だといわれていましたが、まさか、ヒグマに襲い掛かるくらいだなんて! とビックリしました。なばたさんの中で、特に思い入れの深いコビトはどれですか?
やはり、最初に思いついたクサマダラオオコビトですね。クサマダラオオコビトのフィギュアを車に乗せて走っていたとき、草むらをみて、名前を考えていました。よく昆虫の名前に「マダラ」とついているので、「クサマダラ」。「コビト」なのに「オオ」ってついていたら面白いなと思って「クサマダラオオコビト」。この「パっ!」と思いついたときの快感がすごく好きだから、『こびと大図鑑』なんて無謀なこともできたのかもしれません(笑)。そもそも、こいつがいなければ、「こびとづかん」もこんなにシリーズになっていなかったと思います。そういう意味では、クサマダラオオコビトはぼくの人生を変えたコビトですね。
















 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪