●まぜごはんをどうぞ
───内田さんは、マジメなものをマジメに書くのが恥ずかしいのでしょうか(笑)。
恥ずかしいですね。ユーモアがないと。その後2011年に『ぼくたちはなく』(PHP研究所)で三越左千夫少年詩賞をいただき、『しっぽとおっぽ』(岩崎書店)では絵も自分で描きました。今年(2014年)出たのが、『まぜごはん』(銀の鈴社)です。
───『うみがわらっている』と『まぜごはん』は、「ジュニアポエムシリーズ」(銀の鈴社)のなかの一冊ですね。子どもにもわかる言葉で真実の世界をうたう個人詩集のシリーズ。谷川俊太郎さんの『地球へのピクニック』や、やなせたかしさんの『生きているってふしぎだな』など、魅力的な詩集がたくさんあります。1975年以来、ずっと読み継がれている詩集シリーズなんて、すごいですよね。『まぜごはん』は、なんとシリーズ237番目の詩集!
ちなみに『まぜごはん』でいちばん好きな詩は、どれですか。
好きというのはむずかしいけど、わりあい気に入ってるのは、序詞の「ぽぽ」ですね。短くて、いいよね。「ぽぽ」は武鹿悦子さん(2014年『星』日本児童文学者協会賞受賞)もほめてくださっていて。これもなんとな〜く書いたのが、よかったんだと思います。力が抜けているのがいいんだろうな。
───“たんぽぽさん”がかわいらしいですよね。わたしは「ほっきょく」という詩を読んだとき、じわーっと胸にあったかいものがひろがりました。
───じつを言うと、「詩」をどうやって味わったらいいのか、わからないところがあって・・・。
「いい詩」を理解できなくちゃいけないんじゃないか、詩の内容が自分にわかるだろうか、と、つい身構えてしまって。
詩は、感じればいいんであってね。春風のように。秋風のように。そんな詩が書けたら、言うことはないですよね。
ふわっと風にふれるみたいに、言葉がたちあがってくる。それをただ感じればいいんだと思いますね。

───「うしかもしか」の詩を声に出して読むと、ふだん詩なんて興味を示さない小学生の息子が「ん?」という顔で、ぱっとこちらを見るんです。あらためて、「そうか。詩は感じるものなんだ」とふに落ちた気がします!
『きんじょのきんぎょ』と『まぜごはん』では長野ヒデ子さんが絵を描かれていますが、長野さんとは長いおつきあいなんですか?
そうですね。最初の少年詩集が出る前から、詩を読んでもらったりしていますからね。なぜ今回長野ヒデ子さんが絵を描いてくださったかというと、長野さんからメールが来たんですよ。「内田さん、銀の鈴社に、次の詩集のための詩を届けてるでしょ」と。そしたら「絵は長野さんですよ」と返事しないとね(笑)。ただし条件がひとつあります、今度は絵の描き方を変えてくださいね、と。『きんじょのきんぎょ』は筆ペンで描かれているでしょう。だから、『まぜごはん』は鉛筆でもクレヨンでもペンでもいいから、変えてくださいって。
───だから2冊は絵のタッチがちがったんですね。
詩の絵ってむずかしいんだよね。力みすぎると詩を食っちゃう。今回長野さんが描いてくださった絵は、さらに力が抜けていい感じですよね。
───内田さんの詩集は、あとがきも、毎回おもしろくて素敵です。あとがきにあるように「まぜごはんをどうぞ」と言われたら「いただきます」と言いたくなります(笑)。
●胸キュンは恥ずかしいけど、ヘンはすき――『ともだちや』誕生秘話
───ところで、マジメなものは恥ずかしいとおっしゃっていましたが、「おれたちともだち」シリーズは、友情がテーマで、ユニークだけどじわ〜っと感動するお話ばかりですよね(笑)。

『ともだちや』(シリーズ1作目)はねえ、書いてすぐ「これは売れる」とわかりました。しみじみしているから。胸キュンだから。いや、ほんとですよ。ナンセンスユーモアなんか書きつづけているとだいたいわかるわけですよ。初版、絶版をくりかえしているとね。ああ、胸キュンなら売れるよねえ、と。でも胸キュンは嫌なのね。だからそういうものができると、すぐ破いて捨てていたんです。でも『ともだちや』は胸キュンだけど、ちょっとヘンだったんだよね。ヘンは好きだから、破かずにぶらさげておいたの。
そしたら偕成社の編集者が、自分はもうすぐ退職するから、退職祝にナンセンスじゃない作品をください、って言うんですよ。そのとき『ともだちや』しかなかったんだよねえ。しょうがないからそれを送ったら、翌日すぐ電話が来ました。「シリーズにするから、続きを書いてください」って。内心「しまった!」と思いました。そのときは貧乏どん底だし、奥さんにはわるいんだけど、売れるのはなんか嫌だなあと。
───胸キュンものは破って捨てていたなんて。ほんとうに嫌だったんですか?
講演会で自分の本について話す機会があっても、『ともだちや』にはぜったい触れなかったですからね。
福岡に「エルマー」という書店がありまして、わたしの私設応援団をしてくださっている方たちがいるんですが、あるとき講演会にまねかれて、会のあとに20人くらいで飲んだりしゃべったりしていたんです。そうすると、みーんな『ともだちや』の話をするんですね。わたしは、なんだかムカ〜っときてしまって、黙ってたんです。
───ええっ、ムカ〜っと!?
ええ。とうとう頭にきちゃってね。「みなさんは、わたしのナンセンスが好きで応援してくださるんでしょ。どうして『ともだちや』みたいな作品が好きなんですか」と言ったんです。そしたら「だって両方とも好きなんだもん」と言われて。
そのとたん、ああ、両方とも好きっていうのがあるんだ、と。そりゃあわたしだって奥さんが好きで、奥さんじゃないひとも好きだから(笑)。ああ、あるある、それはわかる、と(笑)。それからは、自分の心から出たものは、自分の作品であるっていうふうにしちゃったわけです。
───へえ〜〜〜っ。なるほど(笑)。
いまはいろいろ書きますよ。『うみべのいす』や『はくちょう』も書きますし。でもその当時はね・・・。『ともだちや』が出たのは57歳くらいのときでしょ。まだそういう境地には至ってなかったんです。 でも『ともだちや』が成功したのは、降矢ななさんの絵の力が大きいですね。最初に降矢さんから出てきた絵を見たとき思ったのは「しめた!」ってことですよ。じつは事前に降矢さんから、登場する動物たちは洋服を着ていますか、と聞かれました。でもわたしはあなたにお願いしようと思ったのだからおまかせします、と。そしたらキツネが頭にゴーグルして、浮き輪ですよ。まさかそんな絵が出てくるとは思わなかった。絵本のだいご味はここですね。想像を超えた、絵に出会う快楽です。
───以前、西村繁男さんにお話をうかがったとき、内田麟太郎さんとどのように絵本を作るのかうかがって、おもしろいなあと思ったことがあります。
(『ようちえんがばけますよ』インタビュー>>>)
『がたごとがたごと』という絵本があるでしょ。あれは言葉の量は多くないんですよね。だからうちの弟は「麟太郎兄ちゃんはずるか(ずるい)」と言うんですね。「がたごとがたごと」と書くばっかりで印税稼いで。でもあの絵本は、20代から知っているヘンな西村繁男さんを喜ばすにはどうしたらいいかと頭をひねって書いたテキストなんです。
長さんと絵本をつくったときの話にもどりますが、長さんに言われて、絵本の文章とは何かを一生懸命考えていたとき、わからないから、映像文化と思われるもののテキスト、つまり脚本やシナリオを図書館で端から読んでみたことがあります。倉本聰さんの「北の国から」や、野田秀樹さんのシナリオをね。そのとき、あぁ、ト書きというのを使えば、文章が少なくてすむな、と思った。
つまり『がたごとがたごと』を例にするならば、テキストは「おきゃくがのります ぞろぞろ ぞろぞろ」「がたごと がたごと」「おきゃくがおります ぞろぞろ ぞろぞろ」だけれども、最後にト書きで(*降りてくるのは、ひとはひとでも、お化けたちである)と書く。そうすることで西村さんは腕をふるうことができるわけです。

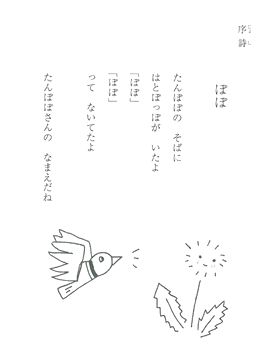
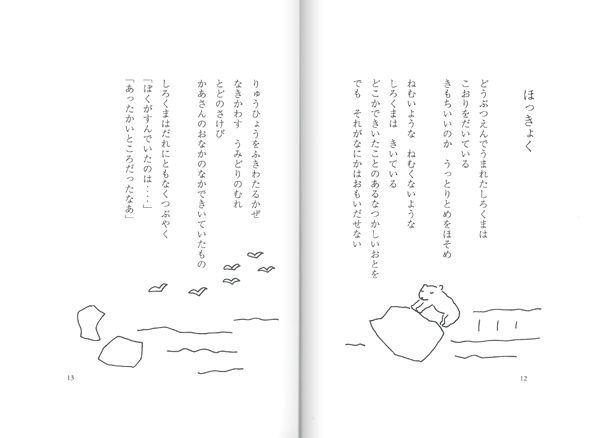
















 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪ 


