ある村にあらわれた、なぞの穴。 なんでものみこんでくれる穴のおかげで 都会はきれいになっていったが……。 庭のすみで見つけた鏡のなかには なんと犬が住んでいた! 五郎くんはあることを思いついて……。 星新一の名作「おーい でてこーい」と もう一遍をお届け。
●絵本の絵と挿画の違いを、作品を通して感じました。
───ここからは1作品ずつ、おはなしを伺いたいと思います。まず、星新一ショートショート集の中でも代表作と言われている「おーい でてこーい」と「鏡のなかの犬」を担当された中島さんにいろいろ伺いたいと思います。
中島:よろしくお願いします。
───中島さんは普段、書籍のカバーや挿画を中心に活躍されていますよね。今回、1冊の絵本の絵を担当されるということで、難しさを感じる部分はありましたか?
中島:そうですね、書籍の挿画や挿絵を描く場合、おはなしを読み込んで、その中で一番印象的な場面を描き、カバーイラストは物語全体の雰囲気を出せるよう一枚の絵に描きます。でも、絵本は一枚の絵ではなく、一作の作品でつながりのある絵を描く必要があるので、描くための考え方も違いました。ひとつの場面を修正すると、他の場面にも影響が出るので、合わせて修正したり。ひとつの物語を描いている間は、モチベーションを同じに保ちたいので、その持続がイラストと違い長時間だったので大変でした。

中島梨絵さん
───たしかに、何ページも同じモチベーションで絵に対峙するのは、大変そうです。今回のシリーズでは、原作通りの文章が掲載されていることも特徴ですが、絵を描くのに苦労したところはありましたか?
中島:「おーい でてこーい」は、台風でできた1メートルくらいの穴に、人々がいろいろな物を捨てていくというはなしなのですが、文章には「外務省や防衛庁から、不要になった機密書類」や「伝染病の実験に使われた動物の死体」、「都会の汚物」、さらに「原子炉のカス」といった表現が使われていました。これをどこまでリアルに絵に描いたらいいかは悩み試行錯誤しました。
───穴を中心に、いろいろなものを捨てていく人たちが描かれているシーン。徐々に無関心になっていく姿がとてもリアルに描かれていて、ゾクッとしました。
中島:実は、これでもだいぶマイルドになっているんです。最初は、「浮浪者の死体」の体の一部を描いていたりしました。でも、やり取りの中で、あまりショッキングな絵は描かない方が良いとアドバイスをいただいて、今の形に落ち着きました。
───穴の中に捨てたいものが捨てられるたびに、空がどんどん澄んだ色になっていくのも、とても印象的でした。
中島:空の色はだんだん綺麗に見えるように描きました。自然な青空から綺麗な青空へ、そして綺麗すぎて不自然に見えるくらいの空の色に。この作品は最後のオチが特にインパクトがありますから、穴によって美しく澄んだ空から、何かが起こる……そのギャップを表現できればと思って描きました。
───建築中のビルの鉄骨の上で、空を見上げる作業員と、隣のビルから彼を見ているような会社員の女性の姿も、なぜか気になりました。
中島:実は、この2人は作品の中で、常に登場しているキャラクターなんです。最初は子どもの姿で出てきていて、木登りをしながら、大人たちの様子を見ています。物語のラストでは成長した姿で、「おーい、でてこーい」という声を耳にする。この描写は、原作には特に描かれていないものなのですが、子どもたち2人で時間の経過を表せればと思い描きました。

このページに出てくる2人は、子どもの姿で要所要所に登場します。
───男の子と女の子が成長していることを通して、物語の中の時間経過がより読者に伝わりますね。このような絵で見せる工夫は、ほかにもありますか?
中島:原作は1960年前後に発表されていますが、2作品とも日常が舞台のおはなしなので、今、絵本を手にする方たちに違和感のない描写になるよう、現実にあるものは忠実に描こうと思いました。例えば、『鏡のなかの犬』の中に、おふろ屋の裏の空き地が出てくるのですが、今の銭湯の裏側がどうなっているか分からなかったので、高橋さんにお願いして資料をいただいたり、近くに裏側が道路に面している銭湯があったのでその銭湯を少しアレンジして銭湯とわかるように描いています。
───木がたくさん置いてあるから、昔風の描写なのかと思ったのですが、今どきの銭湯もこういう感じなのですね。
風讃社・高橋:聞くところによると、燃料に灯油だけを使うと、コストがかかってしまうそうで、木を燃やして効率化を図っているそうです。『おーい でてこーい/鏡のなかの犬』は、星マリナさんも特に思い入れの深い作品らしく、絵についてのアドバイスをたくさんいただいたんです。その要望に中島さんも最大限応えてくださり、何度も描き直して、より良いものを仕上げてくれました。
───リアルな描写を追求していくことで、おはなしの不思議さがより引き立ちますね。
「鏡のなかの犬」は、鏡の中から出てきた真っ白な犬と、少年の交流がとても微笑ましいおはなしだと思いました。しかし、後半で、子どもの狡猾さ、欲深さが浮き彫りになり、取り返しのつかない別れが訪れます。背景を描かず、色で書き出された心情や割れた鏡の鋭さなど、絵から感じ取れました。
中島:ありがとうございます。鏡が割れた場面は、割れた破片や、破片に移る少年の姿など、リアルに描かないと読者がおはなしの世界からスッと離れていってしまうと思いました。なので、鏡の割れ方を調べてそれを参考にして構図を考えました。
───おはなしはもちろん、見返しや表紙も工夫されているように思いました。
中島:前見返しは「おーい でてこーい」の穴、後ろ見返しは「鏡のなかの犬」の鏡をイメージしています。表紙は表と裏で2つの作品がそれぞれ表紙になっているように描いています。
田中:ぼく、この表紙がすごく作品を表していて好きなんです。子どもだけ穴の本当の意味に気づいているような、上を向いた表情も良いですよね。
中島:ありがとうございます。
●「夜」を舞台にした、近未来の物語。
- 友を失った夜/とりひき
- 作:星 新一
絵:田中 六大 - 出版社:三起商行(ミキハウス)
未来の夜のニュース。 人類が失おうとしている 「友」とは、いったい誰? ……悪魔が人間の魂をねらっている! 「とりひき」をしてしまった男は はたしてどうなってしまうのか? ちょっと未来の夜のおはなしです。
───田中六大さんは、ご自身で文章と絵を描かれた作品も、作家さんの文章に絵を描いた絵本もたくさん出版されています。今回、学生時代にハマった星新一さんの作品の絵ということで、緊張などはありましたか?
田中:もちろん、お話をいただいたときは、ぼくに描けるだろうかとすごくドキドキしました。作品を読んでみると、星新一さんらしい近未来のおはなしなんですが、ちょっと怪しい悪魔とか出てきて「面白いな」と思いました。

田中六大さん
───絵を描くときに苦労したことはありますか?
田中:星新一さんの作品は、ショートショートという特性上、物語の舞台があまり大きく変わらないんです。「友を失った夜」は、老婦人の部屋のテレビの前から基本的に動かないし、「とりひき」も、エフ博士の家の玄関と、室内しか出てきません。それを忠実に絵本で描こうとすると、とても退屈な絵になってしまうので、どうやって絵で見せるのが面白いか、頭を悩ませました。
───「友を失った夜」は、祖母と孫の会話のやり取りで進んでいきますが、絵本では、ジャングルが出てきたり、近未来のゾウの飼育されている様子が描かれていたり、すごく絵を味わうことができる作品だと思いました。
田中:実は最初のラフは、今のものとかなり違っていて、星新一さんが作品を発表した時代から見た、未来の姿を描いていたんです。テレビの形も、街並みもかなり違いました。しかし、編集者さんから「今の子どもたちが想像する未来の都市を描いてください」と言われて、すごく悩みました。例えばテレビ。今は4K、8Kテレビとかが発売されていますよね。でも、今よりも未来だと、テレビの概念から変わってしまっているかもしれない。ニュースの場面は、未来のテレビの描写なんです。

初期のころのラフを見せていただきました。

「友を失った夜」
───画面の中の景色が、私たちの身近に迫ってくるような感じなんですね。
田中:でも、男の子が持っている「宇宙生物のオモチャ」はわりとレトロな感じだったり……。この辺は、ぼくの絵のテイストを生かさせてもらいました(笑)。
───男の子と祖母の感じていることにもギャップがあって、読者に考えさせる内容だと思いました。人類の未来を思う祖母の表情、視線が印象に残りました。
田中:ここの表情はすごく難しくて、編集者さんと話をしながら、何度も描き直しました。
───最後の場面は、特に美しい情景だと感じるのですが、祖母の表情を見ていると、ほほえましいばかりではない感情が湧いてきます。
後半の「とりひき」は田中さんもおっしゃっているように、前半と一転して、怪しい可笑しさ満載の作品ですね。
田中:なによりも悪魔が、お笑い芸人さんみたいにインチキ感あふれる容姿ですからね(笑)。
───ある家にやってきた悪魔が、男に「どんな勝負事にも勝てる力」を与えます。しかし、その力と引き換えに、死んだ後の魂を悪魔に差し出すという「とりひき」をするというおはなし。これだけ聞くと、人間側に大変不利な内容だと思うのですが、ラストのオチが星新一さんならではなおはなしですよね。
田中:そうなんです。悪魔というファンタジーのキャラクターが、SFに登場するとこんな展開になるんだ!という驚きがありますよね。
───悪魔ととりひきをした男が実は……だったという、ラストが印象的でした。ちなみに、友人として、エフ博士の家にやってきた人ですが、「友を失った夜」のアナウンサーと同じ人に見えるのですが……。
田中:はい。今回、未来の話ということで、「友を失った夜」と「とりひき」の中で、共通する設定やイラストを何点か潜ませています。エフ博士の友人は、「友を失った夜」のアナウンサーと同一人物です。
───何点か……ということは、ほかにも2つの作品で共通しているところがあるのですか?
田中:あと2つほど、作品をつなげるように意識的に描いた描写があります。ぜひ、探してみてください。
───すごく気になります……。そういう遊びができるのも、2作品が1冊に入っている、このシリーズの面白さですね。ちなみに、表紙も2作品が絶妙に混ざり合っていて、とても印象的だと思いました。
田中:表紙に関しては、ほかの2作品とイメージが被らないように編集者さんからいろいろ提案してもらいました。その中で、『友を失った夜/とりひき』は2つとも未来を舞台にした作品なので、両方の要素が混ざった表紙の方が面白いだろうということになり、構図を考えました。
───エフ博士とアナウンサーが同じ車に乗っていたり、「宇宙生物のオモチャ」の広告が出ていたり、絵で楽しめる表紙ですよね。
田中:描き上げてから気づいたのですが、「友を失った夜」も「とりひき」も両方とも夜のおはなしなんですよね。今まで、あまり暗いタッチをずっと描くことはなかったので、1冊のほとんどが、青系か黒系の絵を描いたのは新鮮でした。
───落ち着いた雰囲気の絵があるからこそ、「とりひき」の悪魔の交渉の部分はカラフルで、パッと目を引きますね。
田中:悪魔を描くのは好きなので、すごく楽しかったですね。でも、星新一さんの作品というと、どうしても長年挿絵を担当された真鍋博さん(※)の印象が強くて、絵を描く前は、イメージに引っ張られてしまうかな……と思ったのですが、ぼくの作風は、すごく泥臭い感じだったので、描き上げてみたら、全然違うものになっていました(笑)。
※真鍋博……イラストレーター。星新一ショートショート集の挿絵を多く描き、名コンビと言われていた。
中島:私は、田中さんの未来の建物がすごく好きですよ。月明りで建物が浮かび上がってくる感じも、この作品とすごく合っているなぁと思いました。

田中:そうですか? 自分ではもっと無機質な感じの都市を描きたかったんですが、そういっていただけるとちょっと安心しますね。







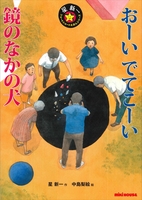
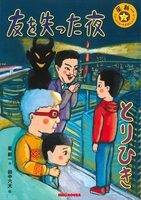







 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪ 

