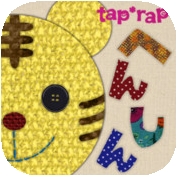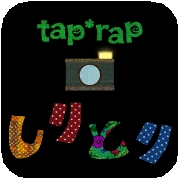●「親しみやすく、教育現場でも活用できるデジタルえほん」への思い
遊び心満載の「デジタルえほんミュージアム」を企画した大日本印刷の中津井直子さん、吉岡康明さん、大日本印刷と共同で、「みらいのえほんプロジェクト」メンバーとして活動している、株式会社デジタルえほんの石戸奈々子さん、李里さんにお話を伺いました。
───今日はオープン前の「デジタルえほんミュージアム」を案内していただき、ありがとうございました。どのコーナーもとてもよく考えられていて、夢中になって遊んでしまいました(笑)。この「デジタルえほんミュージアム」はどういった経緯でオープンに至ったのか、とても気になりました。
中津井:そのお話をするためには、私たち大日本印刷が電子出版に対してどう考えてきたかをお伝えいたしますと…。大日本印刷株式会社は印刷会社として、長く出版業界に関わってきました。2010年、いよいよ本格的に電子出版の取組みを開始したとき、デジタルの世界でも絵本が重要なジャンルになるだろうと感じました。そのような中で、すぐれた新しいデジタル絵本の制作に関わっていこうと決めましたが、具体的な方法を模索していました。
吉岡:そんなとき、デジタルえほんのワークショップで活躍されている石戸さんと季里さんにお会いし、我々と思いを同じくしていることを感じて、共同プロジェクトを立ち上げる運びとなりました。
───その共同プロジェクトの名前が「みらいのえほんプロジェクト」ですね。
中津井:はい。「みらいのえほんプロジェクト」は、私たち大日本印刷(DNP)と、子ども向けデジタルコンテンツの企画・制作を手がける株式会社デジタルえほんが「子ども達に親しみやすく、保育園や学童などの教育現場においても活用できるデジタルえほんの企画制作」を目的として立ち上げたプロジェクトです。今回の「デジタルえほんミュージアム」でも取り上げている、「tap*rap」シリーズもこの「みらいのえほんプロジェクト」の一環としてリリースされました。この活動が注目されて、今回の子ども向けの体験スペースとして「デジタルえほんミュージアム」を開設することになったのです。
●「タップだけで進んでいく」、シンプルな発想から生まれた「tap*rap」シリーズ
───「tap*rap」シリーズは現在、何作品発表されているのでしょうか?
中津井:2012年2月に『tap*rapしりとり』をリリースしまして、その後、『tap*rapフォトしりとり』『tap*rapへんしん』『tap*rapつくるへんしん』と、現在までに4作品出ています。
───『tap*rapしりとり』は画面をタッチしていくと、粒子が集まってきて、しりとりの答えの絵が現れるというシンプルだけど、すごく楽しい作品だと思いました。これまでにない新感覚のしりとり絵本というコンセプトと、その操作性が高く評価され、2012年にはシリーズとしてグッドデザイン賞とキッズデザイン賞を受賞されましたよね。「tap*rap」シリーズの第一弾をしりとり絵本にしようと思ったのは何故ですか?
季里:私は以前ゲーム業界にいたんですが、最近はマニュアルを読まないとプレイできない複雑な作品が増えてきていたので、説明を読んだり、メニューから選ぶのではなくシンプルに画面をタップするだけで進んでいくアプリが作れたら良いなと考えていたんです。
吉岡:デジタルえほんさんからそのお話を伺ったとき、社内でその実現方法をいろいろ検討して「パネルをタッチすると、タッチした部分に砂鉄が集まってくる」というインターフェイスと動きを提案し、その技術を活用したデジタルえほんを作るという方向が決まりました。
石戸:実際にしりとりをやっているときって、言葉がすぐに頭に浮かぶのではなく、「り」だったら「り、り、り…」と頭の中で、最初の言葉を復唱しながら言葉を探していくと思うんです。その脳の働きと、指でタップするリズム、タップして見えてくる絵の成立具合が合致したら、作品としてとても面白いものになるのではと思い、しりとりをシリーズの1作目にすることが決まりました。
季里:砂鉄を見た瞬間、いける!と思いました。タップすると集まる粒子を見て、音もだんだん集まって来るイメージがわきました。絵の完成と同時に、集まった音も音楽か言葉になって欲しかった。音をうまく使い、紙の絵本では絶対出来ない作品をつくりたかったのです。砂鉄が集まって絵になるなら、逆に絵が
バラバラになることもできるのではないか。砂鉄が集まったり、爆発したりするもの。何だろう..って考え続けてました。
───制作の中で大変だったことはありますか?

吉岡:アプリ開発に関しては大日本印刷の持つ技術手法を使って、しりとりの答えが出るまでのタップ回数を何回にするのが適当か…ということや、粒子の大きさや、粒子の飛ばし方、集まり方の微妙なニュアンスなど、子ども達が気持ちよく楽しむための微調整をしながら何度も試作を繰り返しました。
石戸:私と季里さんは原案を考えるため…ただひたすらしりとりのネタを考えていましたね。
季里:私たちは日中に会って話をすることがなかなかできなかったので、打ち合わせはもっぱらスカイプ(Skype:IP電話)を使っていました。『tap*rapしりとり』のときは「しりとりのあらゆるパターンを出そう!」って2人で決めて、明け方近くまでしりとりを出し合ったこともありました。
───スカイプを使って、しりとりをしたんですか?
石戸:そうなんです(笑)。ただ、やみくもに言葉をつなげるのではなく、ビジュアルで見せる絵本なので、色がカラフルで、分かりやすくて、子どもが好きなもの…と考えてしりとりをするとどうしても長く続かなくて…。「どんなに頑張っても13パターンしか出てきませんでした!」って、大日本印刷さんに泣きながら報告したこともありました。
季里:今考えてもあのやりとりは相当クレイジーでしたね(笑)。
石戸:2人で考えたしりとりのアイディアを、季里さんがビジュアルにして、大日本印刷さんにtap*rapの試作品を作ってもらって。それから実際に子ども達に使ってもらうのですが、そこでボツになった案もかなりあります。
───『tap*rapしりとり』の後は、自分でしりとりを考えて作れる『tap*rapフォトしりとり』をリリースされていますよね。実は今回、絵本ナビスタッフが試してみたんです。
一同:本当ですか!すごく嬉しいです。
吉岡:しりとりの作り方については、議論を重ねて最終的に端末の写真撮影と音声録音機能を使うことにしたのですが、デジタルの部分とアナログの部分がうまく融合して創造力を育くめる良いものになったと思っています。
───やってみると、自分で写真を撮って、それに自分で声も入れられて、完成品がすごく大切な作品に感じられました。

季里:私達プロジェクトメンバーも「tap*rapフォトしりとり」で、子ども達が自分で作って感じる達成感というか、幸福感を感じてほしいと思って作りました。
石戸:少し大げさかもしれないですが、今、表現の世界はすごく敷居が高くなっていると感じる部分が多くて、なかなか自分で作ったり、表現したりする場面が少なくなっていると思うんです。でも、元々表現することは自由で身近なものだったはずなんです。それをデジタルの力を借りて少しでも自由に表現できるようになれば…。何か1つでも自分で表現できる手段を見つけた子はものすごく成長していくのではないかと思い開発しました。
中津井:自分でテーマを考えたり、テーマに沿って作品を作るのも面白いし、創造力が付きますよね。

───『tap*rapへんしん』の後にも自分で動物を考えて作れる 『tap*rapつくるへんしん』をリリースされてますよね。これも『tap*rapフォトしりとり』と同じ思いで作られたのでしょうか?
石戸:はい。『tap*rapつくるへんしん』では、組み合わせの計算上、1000万通りの動物の顔が作れるようになっています。子どもが思いつくままにオリジナルの動物を考えてくれたら嬉しいですね。
───1000万通り!すごい数ですね! 『tap*rapへんしん』の制作で苦労したことはありますか?
石戸:『tap*rapへんしん』の絵を見ていただくと分かるのですが、全て丸かそれに近い形で動物達が作られているんです。そのため、丸い形で不自然でなく、子どもに人気のある動物を考えるのに少し苦労しました。 季里:ウサギとゾウは絶対入れたかったので、ウサギの耳とゾウの鼻をどうするか悩みましたね。

───動物の絵に使われている、毛糸や布を使った素材がとてもあたたかい感じがして良いですよね。
季里:これは私が昔着ていた、服の端切れとかをパソコンにスキャンして作りました。 石戸:季里さんは、身近にない素材がほしいときは、日暮里の繊維街に買出しに行ったりしてました(笑)。この『tap*rapへんしん』では、右下に作った「リセットボタン」が子ども達にすごく人気なんです。

───子どもってつみきを積み上げることよりも、壊すことの方が楽しかったりしますよね。それと同じ気持ちなのかもしれないですね…(笑)。













 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪