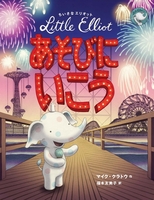●祖母のプレゼントから、エリオットは誕生しました。
磯崎:「ちいさなエリオット」シリーズは、主人公のエリオットとねずみくんのキャラクターがとてもかわいくて、日本の子どもたちにも非常に人気があります。私自身もこの作品が大好きなのですが、何度も読み返すうちに、物語からどこか切ない雰囲気が漂ってくるように感じました。
例えば、主人公のエリオット。彼は周りに親やきょうだいがいない、たったひとりという設定ですよね。
これはとても孤独なことだと思うのですが、このような設定にした理由は何かあるのでしょうか?
マイク:エリオットの物語が生まれた背景には、私自身の体験が強く関わってきていると言えます。
例えば、1作目の『ちいさなエリオット おおきなまちで』。この絵本の中に、エリオットがカップケーキを買いに行く場面が出てきます。

作者のマイク・クラトウさん
磯崎:小さすぎて気づいてもらえず、結局買えなかったという場面ですね。
マイク:そうです。これはぼくの子どもの頃の経験がベースにあります。お母さんに買い物を頼まれて出かけていくんだけど、カウンターが高すぎて、誰も小さいぼくに気づいてくれなかった……ということがありました。そのとき感じた孤独感がぼくの中で強く印象に残っていて、絵を描くようになったとき、このショーウィンドウをのぞいているぞうの絵をよく描いていたんです。
磯崎:それは、絵本を作る前のことですか?
マイク:はい。この場面はある意味ぼく自身のセルフポートレートなんです。ショーウィンドウに並ぶお菓子は、ぼくが人生の中で欲しかったもの全てを表していて、当時のぼくはそれを外から眺めることしかできませんでした。ぼくが眺めているお菓子の中には、「絵本を描くこと」も入っていたんです。

「ちいさなエリオット」シリーズを描くきっかけになった場面。
磯崎:当時は手が届かなかった夢のひとつを、今はしっかりとつかんでいるんですね。ショーウィンドウをのぞいているご自身の姿をぞうに例えて描いたのはなぜですか?
マイク:ぞうは、ぼくが15年ほど前からずっと続けているモチーフです。なぜぞうなのかというと、ぼくが小さい頃、祖母がぞうのぬいぐるみをプレゼントしてくれたんです。ぼくはそのぬいぐるみが大好きでした。
それと、小さいときに観たぞうの映画がとても印象に残っていて……そのぞうは、なんと水玉模様なんです!
そういう子どもの頃の出会いがベースとなって、エリオットというキャラクターが生まれました。

子どもの頃のマイクさん。手にはお気に入りのぞうのぬいぐるみが。
磯崎:一般的にぞうには、大きくて力強いイメージがありますが、エリオットが小さくて水玉模様なのには、そういう理由があったんですね。
マイク:はい。大都会という大きな世界とちいさなエリオットとのコントラストが、物語全体の緊張感を高めるのに効果があることも理由のひとつです。
大きな都会で暮らしたことがなくても、今まで一人ぼっちになったことがなくても、これらの設定のおかげで、エリオットの寂しさが小さい子どもにも伝わりやすくなっていると思います。
磯崎:福本さんは、いつこの物語と出会ったのでしょうか?
福本:私は常日頃から、アメリカの出版社のメルマガやアメリカの書評誌「The Horn Book Magazine」などで新刊情報をチェックしています。『ちいさなエリオット おおきなまちで』もそのときに見かけ、レトロな背景の中に、かわいい水玉のぞうさんがいるのがとても斬新で印象に残っていました。 ちょうどそんな折に、マイクロマガジン社の編集者さんから「ぜひ翻訳してほしい絵本がある」と連絡がありました。それが、この絵本だったのです。すぐに検討させていただき、お引き受けしました。
磯崎:最初に原書を読んだときの印象を教えていただけますか?
福本:絵本の中には、私のよく知っているニューヨークの風景が描かれていて、親しさと懐かしさを感じました。特に最初のエリオットが玄関前の階段を下りてくるシーン、この街並みはニューヨークでよく見かける場所です。 それと、私はよく一人でニューヨークを歩くのですが、街の大きさに飲み込まれそうになって、自分がとてもちっぽけなものになったような気がするのです。ですからエリオットが雑踏の中でふみつぶされそうになったり、タクシーがなかなか拾えなかったりしたときの気持ちが、実感としてよく分かりました。そしてその街で友だちに出会ったときの、ほっとするような幸福感も絵本を読んでとても共感しました。

翻訳家の福本友美子さん
磯崎:現実的な景色の中に、エリオットがとても自然に溶け込んでいるんですよね。
福本:そうですね。リアルな光景の中と、子ども部屋にいるような可愛いぞうさんって一見、相反するようにも思えますが、この作品はとても自然に描かれていて……。そういうところにオリジナリティがあって、とても印象に残りました。
マイク:ありがとうございます。
磯崎:マイクさんご自身がニューヨークにお住まいなことも、絵本の舞台がニューヨークとなった理由のひとつだと思います。ただ、年代は現代ではなく、1940年代なんですよね。
マイク:はい。正確には1939年のニューヨークです。この時代のニューヨークは、建築も車などの工業もファッションも、とにかくあらゆるものが美しくて刺激的でした。そして、当時のニューヨークこそが、今日まで続く、ニューヨークの美的特質を決定付けた時代だと思っています。ぼくは、この時代をとても愛しているので、エリオットの物語の中にずっと留めておきたいと思って選びました。
磯崎:時代背景を知らない子どもたちにも、絵本に描かれている世界の独特な美しさ、はかなさは伝わっていると思います。
マイク:そういっていただけると嬉しいです。ぼくは、古き時代には魔法のような力があると信じています。この時代に設定したことで、エリオットの物語は、まるで古くから語られてきた昔話のように、読者に受け取ってもらえるのではないか。つまり、エリオットがカップケーキを買う場面にインターネットもスマートフォンも出てこなくても、納得してくれるのではないかと思っています。

磯崎:たしかに、現代が舞台のおはなしだったら、「エリオットはお店に行くんじゃなくて、ネット注文すればいいのに」って言う子どもがいるかもしれませんね(笑)。
1940年代の世界に生きるエリオットは、SNSで誰かにつながることもできず、大きな街で誰にも気づかれずに孤独に過ごしています。そんなエリオットですが、ある日、素敵な友だちと出会います。それが「ねずみくん」。ぞうの友だちがねずみというのもとても面白いと思いました。
マイク:シリーズすべてに通じるテーマとして、ぼくは「友情の力」を描きたいと思っています。そのためには、エリオットを深く理解してくれる相棒が必要でした。
そしてその相棒は、エリオットよりも小さいのに、とても大きな存在である必要があったんです。だから、ねずみくんをエリオットの相棒に選びました。
それと、よく「ぞうはねずみを怖がる」って言われているのを知っていますか?
磯崎:そうなんですか?
マイク:はい。でもエリオットはねずみくんを怖がっていません。普通のぞうが怖がるねずみをエリオットは友だちにできる。そんな勇気を持ったぞうだということを、示したかったのです。
あと、ニューヨークにはとてもたくさんねずみがいるんです(笑)。だから設定としてもリアリティがあるかなと思いました。
●シリーズ4冊に込めたテーマとは……。
磯崎:ここからは、シリーズそれぞれについてお話を伺えたらと思います。まず、『おおきなまちで』。マイクさんの中でも、一作目は特に思い入れが強いのではないですか?
マイク:そうですね。特にずっと描き続けていたショーウィンドウをのぞいているぞうの絵を絵本の中で描けたのはとても感慨深いです。
磯崎:私もこの作品は強く印象に残っているシーンが2つあります。ひとつは、大勢の人がエリオットに目もくれず通り過ぎる場面。ここの小さな女の子がエリオットに気づいているのがすごく印象的でした。

マイク:雑踏の中にいるエリオットですが、ここは意識的に上からのぞき込むような構図で描いています。そうすることで、読者である子どもたちに、エリオットの孤独をより感じてもらえるのではないかと思ったんです。
磯崎さんの言うように、よく見ると小さな女の子がエリオットに目を向けています。
でも、エリオットは彼女の視線に気づいていないんです。
エリオット自身が、心を閉ざしている様子を表しています。
磯崎:なるほど。エリオットの周りに空間を作っているのも、彼の孤独感をより強調しているんですね。
マイク:そうです。それと、エリオットは左向きに立ちすくんでいて、人々は右方向に向かっていますよね。ここでも視覚的な効果を使って、物語をよりドラマチックにみせています。
磯崎:エリオットが少し顔を上げて周りを見ていたら、もっと早く自分の孤独から脱することができたのかもしれませんね。
マイク:そうなんです。「人生では、いつも広い視野で見る努力を続けていかなければならない」というのが、この作品のテーマです。
とてつもない孤独を感じたとき、人は周りを見ることができなくなると思います。
でも、そこで勇気を出して一歩外へ出ることで、見えてくる世界、得られる経験は大きく変わってきます。
そのことを、エリオットを通じて、みなさんに感じてもらいたいと思いました。
磯崎:もうひとつ印象に残っているのは、ねずみくんの手助けをしているとき、エリオットが「せかいいち せのたかい ぞうに なったような きぶん!」と言っている場面。
山の頂上から景色を見下ろしているとても幻想的な場面ですが、これはどのようなイメージで絵を描かれたのですか?

マイク:これはエリオットの内面を表している場面です。山の頂上に立っているのは、今まで自分のことをとても小さいと感じていたエリオットが、はじめて「大きい」と感じていることを表現したかったから。
あと、人助けという行為によって、エリオット自身が自分の存在意義を見出したことを表しています。
磯崎:今まで閉ざしていたエリオットの心が開いて、絵に描かれているように視野が広がった瞬間ですね。
マイク:はい。使っている色も、今までの暗くて冷たい色から、暖かくて明るい色に変えています。
磯崎:福本さんにとっても、シリーズの1冊目というのは、とても大事な翻訳作品になるかと思います。翻訳の際、気をつけられたことなどはありますか?
福本:そうですね、この本の原文は難しい表現を使わず、とても簡潔な文章で書かれているんです。絵が全てを物語っている絵本で、淡々とした語り口が魅力です。
なので私も、余計な文章を一切使わずに原書の持つ雰囲気を伝えるよう努力しようと思いました。
簡潔ではあるけれど、行間から滲み出るような何とも言えない優しさみたいなものを、日本語でも伝えたい……という気持ちで訳しました。
磯崎:エリオットがひとりぼっちの場面でも、言葉がとてもやさしいので、読んでいて絶望しないというか、「きっといいことがあるよ!」とエリオットに伝えたくなるような文章だと思いました。
福本:ありがとうございます。
磯崎:実は、『ちいさなエリオット ひとりじゃないよ』が個人的にとても心に刺さった作品なんです。
我が家は息子がひとりっこなので、家族のとても多いねずみくんと自分のことを比べてしまうエリオットがとても他人と思えなくて……。
マイク:そうなんですね。ぼくも今まで、家族と離れて暮らす経験が良くありましたし、友だちと家族のように暮らしていたこともありました。
そんなとき、「家族とはどういうものなのか」というのをよく考えていたんです。
磯崎:改めて「家族」について考えると、一概にこういうものというのは言えないものですね……
マイク:ぼくは血がつながっていなくても、心がすごく強く繋がっていたり、いろいろ助け合ったりするような間柄はすでに「家族」なんだと思っています。
なので、『ちいさなエリオット ひとりじゃないよ』を作ったんです。ここに出てくるねずみくん一族のように、みんなが、身近にいる友人を家族のように思ってサポートし合うような世の中になってくれたら、世の中がもっと良くなっていくんじゃないかなというメッセージです。
磯崎:本当にそうですよね。福本さんは、この作品を手に取ったとき、どう感じましたか?
福本:この作品は、物語としての起承転結がすごく上手くできているんですよね。
エリオットは、家族の集まりに参加するねずみくんを最初は快く送り出します。でも、送り出した後に自分がひとりぼっちになってしまったことに気づくんです。
エリオットの行動を追っていくことで、だんだん寂しさが増していくところが本当に分かりやすく描かれているなって感動しました。
磯崎:大きなビルの中にエリオットひとりだったり、散歩に出かけても出会う人はすべて家族と一緒にいたり……。
小さな子でも、この絵を見てすぐにエリオットの寂しさに気づきますね。

福本:港から海を見ている場面と映画館の場面なんて、寂しさの極致という感じで……。
文章なんていらないくらいの物語る絵の力だと思うんですね。読んでいて、ここで本当にじわっと涙をね、浮かべる子もいるんじゃないかしら。
磯崎:「エリオットが寂しがっているよ。ねずみくん、早く帰ってきて!」って思っているところにようやく現れるねずみくん! それだけではなく、嬉しいサプライズもあって……。
そこからの展開に「よかったね〜、エリオット!」と感動! 私、最後の場面が本当に大好きなんです。
マイク:ぼくもとても好きな場面です。見た目は全然違うけれど、愛情が結び付いて家族になるということを感じてもらいたくて描きました。
福本:マイクさんの思い、読者にすごく伝わっていると思います。








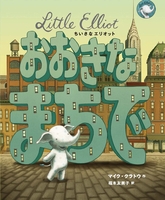









 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪