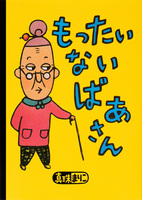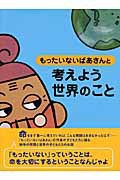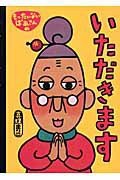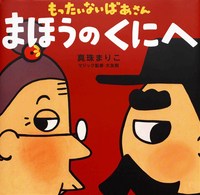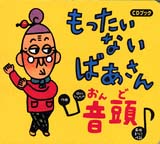●もったいないには愛がある
───毎日新聞の連載「もったいないばあさん日記」が、もう長くつづいていますね。

毎日新聞連載「もったいないばあさん日記」の記念すべき初回。(「毎日新聞」2005年10月26日(水)付より)※毎月第4水曜日に現在も「本はともだち」コーナーにて好評連載中今年100回を超えて10年目に入りました。もったいないばあさんの人となり、日常のくらしぶりなどがよくわかる内容です。ちょっと深くていい話がもりだくさんなんですよ。
初回はおかずの残りものをおいしくたべさせてくれる「もったいない焼きスペシャル」が有名なお好み焼きやさんの話。「わし、お好み焼きを愛しとるんや」と店の主人が言います。それに対してもったいないばあさんは「もったいないには愛がある。愛があるからもったいない。」と言って締めくくります。
───愛があるからもったいない。いい言葉ですね!
「もったいないばあさん」の「もったいない」っていったいなんだろう。いろいろなところで連載をして、絵本をつくっていくなかでだんだんわかってきたことがあります。
読者の小さな男の子に、「もったいないばあさんって、けちんぼのおばあちゃんだね」って言われたことがあるんですが、なんかちがうんじゃないかなと思ったんです。なにがちがうんだろうって、もう一度考えました。
「もったいない」という言葉には、つくってくれた人への感謝の気持ち、思いやりのやさしい気持ち、愛情がこめられています。大事にしたいから、「もったいない」なんですよね。だけどケチは、自分だけのものだとか、人にはあげたくないというニュアンスが入っている、執着だと思うんです。
MOTTAINAI運動に力を注いだマータイさんは、リユース(再使用)、リデュース(消費削減)、リサイクル(再生利用)の3Rだけではなくて、4つめのR、リスペクト(相手を尊重すること)があるからこそ、もったいないは世界平和につながるのだ、とおっしゃっていました。資源は限られているから、奪い合えば争いが起きる。「もったいない」の心で皆が分け合えば、平和な世界ができるのだと。
マータイさんともったいないばあさんは、同じことをメッセージとして発しています。マータイさんは、だからこそ期待をこめて「もったいないばあさん、がんばってね」と言ってくれたのだろうと思うんです。
───そういえば、もったいないばあさんのかたき役、「がちゃばあ」というケチのおばあさんが、『もったいないこと してないかい?』に出てきますね。

がちゃばあは、本名、金山がちゃこさん。「がちゃばあ」は、新しいものが大好きで、ものを買いかえるたびにまだ使えるものを山ほど捨てて、いつももったいないばあさんに怒られています。そのうえ、自分のものは自分だけと執着する。お金持ちなのに、けちんぼ。だけどなぜか憎めないおばちゃんです。
───たしかに一般的には、節約とケチって、ひとまとめになりがちかも・・・。
「もったいない」はただの節約や、ケチじゃないですよね。もったいないばあさんは、七五三のときに買ってもらったかんざしのように、愛着のあるものを長く大事につかいます。
連載をはじめたときは、暗中模索というか、もったいないばあさんらしい「もったいない」をどんなふうに表現していったらいいか、とても悩みました。暮らしの知恵を本で読んだり、ひとに話を聞いたりしましたが、やっぱり自分でやってみないと書けないから、ぜんぶ試してみました。
───えっ、連載に出てくる、もったいないばあさんの知恵を、ぜんぶご自身でやってみるんですか? それはたいへん・・・。

たいへんだけど、興味もあって楽しんでやっています。自分の手をうごかしていろいろ試すうちに、作者である私の生活もずいぶん変わりました。保存食も手作りするようになりましたし。そしてそれが楽しいっていうこともわかって、よかったです。
───真珠まりこさんは、絵本ができあがるまでに、何度も子どもたちに読み聞かせをされるとか。
全国をお話会などで飛び回り、とても行動的でいらっしゃると感じるんですが、日々の行動から作品が生まれる実感はありますか?
そうですね、あるかもしれません。
今回も、『もったいないばあさんの てんごくと じごくのはなし』ができあがるまでに、いろいろなところで読みました。お話会や講演会で、最後にちょっとしたサービスのつもりで「まだ出てないんですけど、読みますね」とカラーの校正紙などを広げながら読むと、みなさん喜んで聞いてくださいました。
昨日は、幼稚園の4歳児クラスで読んでみたんですけど、裏表紙のスプーン(天国のスプーンと地獄のスプーン)に、熱心に反応してくれました(笑)。みんなで「スプーン、スプーン!」って指さして。そして、地獄の人たちが食べにくいことを、すごーく気にしていました(笑)。ちっちゃい子たちなりに、「口に入らない」ってことを、いっしょうけんめい想像してたんじゃないかなあと思います。「こんなにながーいスプーンだから、じぶんでたべようとおもったらたべにくくて、いっぱいこぼしちゃったんだね」って話したら、「ふうーん」って(笑)。
───子どもたちなりに、いっしょうけんめい考えてる(笑)。出版後の反応が楽しみですね。
絵本の中では、なにがどうしてもったいないということは言っていないんですが、なぜ地獄ではもったいないことがあって、天国ではなかったか、大切なことは何か、ということまで、自分で考えるようになってくれたらいいなと思います。
「もったいないばあさんのワールドレポート展」では、「自分さえよければと思わず、分け合う気持ちがあれば平和な世界がかならずできる」というメッセージを伝えていますが、これは、『もったいないばあさんの てんごくと じごくのはなし』にも共通する大事なメッセージ。
スープは、赤ちゃんからお年寄りまで、みんなが食べられるやさしい食べもの。そして日本だけでなく、世界中の人たちが共通して食べているもの。もったいないばあさんのメッセージを、絵本を通して世界中の人たちに伝えられたらうれしいです。
───もったいないばあさん誕生10年間のお話をうかがって、ますますこのシリーズの新作が楽しみになりました!
今後はどんなお仕事をされていきたいですか?
「もったいないばあさん」は、もはやライフワーク。今の時代に必要なメッセージを伝えるおばあさんだと、私は本当に思っています。
「もったいない」は元々仏教の言葉で、命の大切さを伝えることばなのだそうです。
自然といただく命に感謝して大切にすること、命があるものを粗末にするのはもったいないということ、命こそが一番大切なものだということなど、これからも、大事なことをできるだけわかりやすく伝えていけたらと思います。
そして、楽しい絵本も、こんな本が作りたかったと思えるような満足のいく作品も、ひとつひとつ大事につくっていきたいです。
───ありがとうございました!

真珠まりこさんHP
もったいないばあさんHP
「もったいないばあさん音頭」動画大募集

もったいないばあさん、きょうはありがとうございました!

編集後記(おまけ)
こちらは最初の絵本『もったいないばあさん』のワンシーン。洗面台の絵は、じつはフランスのインテリアが好きな真珠まりこさんが、フランスのインテリア雑誌を見ながら、かわいい!と自分が思えるものを、単純な線にデフォルメしながらこだわって描いたそう。一枚一枚の絵を、愛情をこめてつくりあげていることが、ひしひしと伝わってくるインタビューでした。
『もったいないばあさん』持ちこみのエピソードから、現在のメッセージまで、どんなことも言葉を尽くして真摯にお話してくださいながらも、ちらっと見せてくださるやわらかな表情が、とてもチャーミング!
もったいないばあさんがみんなのアイドル(!?)になったわけが、わかったような気がします。
さて『もったいないばあさんの てんごくと じごくのはなし』は・・・子どもたちがどんな反応をするのか、ぜひ読んでみてくださいね!

インタビュー:磯崎園子(絵本ナビ編集長)
文・構成:大和田佳世(絵本ナビライター)





















 【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット
【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット