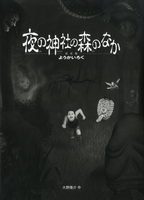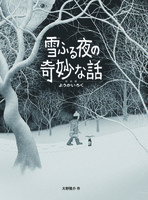●独自に描いたもの、アイヌの妖怪も登場します。
───もう少し妖怪について教えてください。他に、大野さんが独自に描いた妖怪は、どんなものがいますか?
『雪ふる夜の奇妙な話』の雪の枝にいる「いつまで(以津真天)」は、くちばしのある人間のような顔に、蛇のような体、大きな翼、足にするどい爪をもつ妖怪です。これは、古い時代の絵を探したところ、ささっと筆で描いたような線画でした。顔は古い絵に似せましたが、体や毛髪や翼などは触れるような感じにしたいと思って、より立体的に描き加えました。
「イワポソインカラ」「ホヤウカムイ」などは北海道の妖怪です。アイヌに伝わる妖怪で、名前もアイヌの言葉から来ています。「イワポソインカラ」の絵は残っていなかったので、これも文献から姿を創作しました。「ホヤウカムイ」の「カムイ」はアイヌの言葉で「神」なんですね。これも似ているものはあったけれど、姿そのものが描かれているものはなく、大部分は特徴から想像して描きました。

いつまで(以津真天)
オハチスエ

ホヤウカムイ
イワポソインカラ
───カタカナの名前はアイヌの妖怪なのですね。たしかにあまり見たことがないと思いました。
その妖怪の姿がまだ描かれていないと思うと「残念だな」と感じるんです。特徴を調べて絵におこすと、姿を与えられた妖怪が喜んでいるような気がします。
───すでに絵がある妖怪を描くのと、特徴から姿形を想像して描くのと、どちらが楽しいですか?
どちらも楽しいです。どの妖怪を描くのも、全部それぞれちがった楽しさがありますね。

●絵本「ようかいろく」シリーズを描いたきっかけは?
───そもそも、なぜこの2冊を描こうと思ったのですか。
僕はデザインの仕事をはじめたのがわりと遅くて、30歳を過ぎてから、辻村益朗(*)氏の事務所に入ったんですよ。アシスタントみたいな仕事からはじめて、何年か仕事をするうちに「辻村益朗+オーノリュウスケ」とクレジットを入れてもらえるようになりました。
1人立ちするために、それまでデザインしたものをまとめてポートフォリオにして、それを持っていろんな出版社を回っていたときに、今回の絵本を一緒に作ることになる編集者に会いました。しばらくはデザイナーとしてのお付き合いでしたが、あるとき食事の席で、僕が描いていた妖怪の絵を見てもらい、「いいじゃない」「絵本を描いてみたら」と言ってもらったのが「絵本を描いてみよう」と思ったきっかけです。
(*辻村益朗…装幀家・作家。ロングセラーの絵本・児童書を数多く手がける。)

───もともと絵本を描いてみたいと思っていたのですか。
絵本を描きたい気持ちはありました。辻村益朗は、「タンタンの冒険」シリーズをはじめとする福音館書店の本のデザインや、福音館古典童話シリーズの装画を描いたりもしていたので、絵本・児童書の仕事は身近でした。じつは辻村は、伯母の夫。血はつながっていませんが、伯父に当たります。
僕は大学では法学部で、20代は会社を立ち上げたり、バーや建築現場で働いたりと、一つの仕事に定まらない生活をしていました。ノストラダムスの予言を信じて、どうせ自分が29歳のときに世界が終わるはずだからと(笑)。でも世界は終わらなかったし30代になってさてどうしようと(笑)。タクシーの運転手もやりましたが長時間労働のハードな仕事でした。
パソコンを使うことはできたので、グラフィックデザインの仕事を学びたいと考えて、あらためて辻村にきちんと「お願いします」と頭を下げて、弟子入りさせてもらいました。それまではふつうの伯父と甥の関係で、絵もデザインもただ好きというだけで、仕事にしようと思ったことはありませんでした。
当時は、アナログ入稿からデジタル入稿に移行しはじめる初期で、僕の仕事はたとえば手描きのタイトル文字をスキャニングしてデータ化し、カバーや表紙に配置したり…、そういった印刷所に入稿するための一部データを作るアシスタントのような仕事からはじめました。「ちがう、そうじゃない」「ここはもっとこうして」と一つ一つ言われながら、教えられて学んでいきました。
今思えば、小さい頃は伯父から束見本(*)をもらってそれに絵を描いて遊んでいました。仕事で作った束見本がきっとたくさんあったんでしょうね。いらなくなった真っ白い束見本をどんどんくれて、僕はそれを“お絵かき帳”みたいにしていました。もしかしたらそんな体験も、今の絵本作りにつながっているのかなと思います。
(*束見本…見本用に、実際の製本時と同じ紙で作られた本。ページ数や厚さが正確に判断できる。中身は白紙。)
●デザイナーとしてのスキルも生きています。
───妖怪を描くのは、楽しいですか?
すごく楽しいです。描いている妖怪のことをいろいろ想像しながら描いています。
鉛筆やシャープペンシルで1点1点バラバラに描き、描いたものをスキャンしてパソコン上で合体させて、絵本の画面を作っています。舞っている雪は、鉛筆で描いたものを反転させています。
『雪ふる夜の奇妙な話』では主にパソコンで雪がつもっている樹々を描いていますが、『夜の神社の森のなか』の樹々は鉛筆描きが多いです。

パソコン上で一本ダタラの場面を見せてくださる大野さん。

鉛筆で描かれた、舞う雪(上)と雪がつもった地面(下)。

鉛筆で描かれた、松の根の部分。

「ここでうちわを、いただきましょう」(『夜の神社の森のなか』より)
───――モノクロの世界の、美しい樹々や星空に魅せられました。陰影があざやかですよね。「大天狗」の白髪も闇の中に浮かんでいるみたいです。

闇の中の陰影があざやか。タイトル文字(右上)も大野さんの描き文字。
そうですね。奥行きや立体感が画面に出るように、デザイナーとしてのスキルを生かすことができたかなと。絵本は黒と白で描かれていますが、印刷の技術的なことを言うと、黒一色の版ではなく、黒とグレーの2つの版を作りました。黒でコントラストを出すための版を作り、グレーでディティールを表現する版を作りました。そのように2つの版を作って重ねることで深い陰影が出ていると思います。
───黒い絵本って、印刷は難しくないのですか?
難しいです。とくに『夜の神社の森のなか』のほうは、最初の校正では全体が真っ黒に印刷され、絵が見えなくなってしまいました。印刷所とやりとりを重ねて、闇の中の妖怪が見えるようにしていきました(*)。
(*『夜の神社の森のなか』は第50回造本装幀コンクールの日本書籍出版協会理事長賞[児童書・絵本部門]を受賞。)
───印刷段階でも試行錯誤があったのですね。
たとえば見返しの印刷もこだわっているんです。『夜の神社の森のなか』の前見返しで少年たちが遊ぶのを、すでに木の上から見下ろしている妖怪がいますし、後ろ見返しにも妖怪が印刷されています。気づきましたか?
───えっ!?…まったく気づきませんでした! これは…?
どちらも「おとろし」です。全身が長い髪でおおわれている妖怪で、神社やお寺で行儀の悪い行いをすると、突然頭の上から落ちてくる妖怪です。後見返しは、「おとろし」が鳥居から落っこちたあと、また上に登っているところですね。

葉陰の「おとろし」(前見返し、左上)。(『夜の神社の森のなか』より)

よじ登る「おとろし」(後見返し、右下)。(『夜の神社の森のなか』より)
───本当だ〜! 境内のボール遊びも見られてる…。よく目をこらすと、うっすらと「おとろし」の顔が見えます。あらためて見直すと、あちこちに妖怪が隠れているのがわかりますね。
それにしても、『夜の神社の森のなか』で最後に「おとろし」が落っこちてくる場面は本当にこわかったです……。
じつは「おとろし」が落ちてくる場面は、いちばんはじめに描いたんですよ。ぜひ実際に絵を見て、こわさを体験してほしいです。















 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪