●絵本を通じて、日本も戦争をしていたことを伝え続けたい
───この絵本を親子で読む場合、親が『15歳の東京大空襲』を読んでいると、絵本に描かれていない部分にも、いろいろと興味を惹かれるエピソードがあっておもしろいと思いました。
半藤:そうですね。空襲を受けて親父と逃げるときに、私が持ち出したカバンの中身は、絵本だと「友だちからもらった手紙」とありますが、実際はラブレターが3通あったんです。
親父に「身一つで逃げろ」と言われたのに、どうにも捨てられなかった(笑)。
その荷物も、途中で落としちゃったんだけど、落としたおかげで川に落ちたときに溺れずにすんだんですから。
───火に追われていたシーンの赤と、川に落ちて助かったシーンの青のコントラストが、とても印象的です。

火から逃れたものの、今度は溺れそうになった半藤さん。
半藤:文字の本は、残念ながらあまり読まれていないようですが、おかげさまで絵本になったから、若い人にも読んでもらえるとうれしいですね。
実際に東京大空襲を体験した物書きというのは、もう私くらいしかいないと思います。
ただ、語り継ぐのは本当に難しいんですよ。
───どんなところが難しいと思われますか?
半藤:戦争のことをしゃべっていると、だんだんと自分がものすごく元気で勇気があって、火も煙も恐れずに堂々と逃げた人間のように思えてくるんです。
それは真実ではないと思ったので、私自身も40歳くらいまで戦争での体験を語らずにいました。
ところが、元軍人の中には嘘ばかり言うのがいるんです。私はずっと昭和史を勉強していましたから、嘘を指摘すると、「何をぬかすか、この若造が! お前なんか戦争体験もなにもないじゃないか」と怒鳴る人もいました。
だからいっぺん、「俺だって戦争体験があるんだということを見せなきゃならない」と思って、話すことにしたんです。
───そうだったんですね。自分から戦争体験を話したことで、変わったことはありましたか?
半藤:2、3年前かな。墨田区八広に住んでいるという女性が、私の本を読んで「私の父は中川の船頭でした。半藤さんを助けたかどうかはわかりませんが、東京大空襲のとき、船を出して人を助けたと聞いています」と手紙をいただいたことがありました。
昔は「船頭の娘」と言われて、肩身の狭い思いをしていたそうですが、それがお役に立ったことが私の本でわかって、「今は誇らしい気持ちになりました」と。
その女性は、私と同い年くらいの方でした。
───辛い体験を声に出すは覚悟のいることですが、声に出したことによって、新たな事実が判明し、記憶に刻まれるということが、伝えていく意味なのかもしれませんね。
塚本:半藤さんのように経験していないと、全部嘘になってしまいますからね。
戦争を知っている人がいなくなると、戦争がどんなものだったかわからなくなってしまう。僕がこの絵本を作ったのは、僕が小さいころから母に戦争の話を聞かされたように、小さいころから戦争についての絵本を読むことで、日本にも戦争が本当にあったことを記憶に留めておいて欲しいという願いでした。
その「実際にあったことだ」という印象を深めるのは、やっぱり半藤さんのように実際に体験した人が「語る」ことに意味があるんだと。
その思いを凝縮したのが、最後のちかいのページです。

このページの文字と題字は、絵画や木版画をたしなむ半藤さんの手描き文字を使っている。
半藤:このページのセリフは、自分の心の中で最後まで拮抗していたんです。
「絶対」という言葉は使いたくないと。でも、森さんや塚本さんの心の要求もあるのか、どうしても使ってくれと言うんです。
「世の中に『絶対』ということはない」というのは、焼け跡でボーッと立ちながら、ボンクラが一生懸命に考えた哲学でした。
だから、「絶対」だけは永久に使いたくないと思っていました。でも、改めて絵本を読むと、この言葉を使わないと終わらなかったね。
塚本:そうなんです。実は最初のスカイツリーの絵にも意味があって、母の話では、今、スカイツリーが建っている場所に、当時、空襲で亡くなった方のご遺体がたくさん置かれていたそうです。
今でも慰霊碑はありますが、あまり人目に触れる場所ではなくなっています。
そうやって、どんどん忘れ去られるのは、やはり怖いなと思います。
───そのお話を聞くと、現代の風景とのギャップがクローズアップされて、また強いメッセージとなって伝わってきます。
最後に、絵本ナビユーザーにメッセージをお願いします。
半藤:私が伝えたいのは、この最後のページの通りです。
世界中の子どもたちを、もう二度とあんなひどい目に遭わせたくないという思いでこの絵本を作ってもらいました。どうかお子さんたちは、「戦争というものは、子どもだろうが、女性だろうが、容赦ないんだ。非情なものなんだ」ということを、しっかりと肝に銘じて欲しいと、本当に思います。
戦争になると、人の生き死にを間近で見てもなんとも思わなくなっちゃうんですよ。
焼け跡にボーッと立っていたときに、それが情けなくてね。本当に、なんにもなくなっちゃうんです、戦争は。
塚本:20〜30代のお母さん世代からすると、戦争の絵本を読むことは、楽しい絵本体験とは対極にあるかもしれません。
でも、次の世代にバトンを渡すという意味でも、子どもたちに読んでもらいたいです。
僕は『焼けあとのちかい』を含めると戦争に関する絵本を4冊ほど出していますが、本当はもう描きたくないとも思っています。でも誰かが形にしないと、どんどん消えて行ってしまうので、黙っていられなくなっちゃうんです。
僕が知っている限りの戦争の本を、これからも描いていこうと思っています。
絵本作家ができることは、絵本を描くことですから。だから絵本を読んで、いろんな人にどんどん想いを繋げてもらえるとうれしいです。
───貴重なお話をたくさんしていただいて、本当にありがとうございました。

インタビュアー/木村春子
文・構成/中村美奈子
写真/所靖子














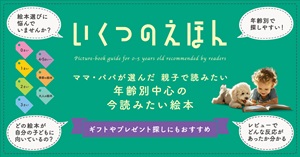
 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪ 


