●引き受けることを逡巡した作家もいたかもしれない
筒井:今回、作家に依頼するにあたり、自分自身もあの日からのことについて文章を書いたのですが、そのときに「これはしんどい仕事だ」と思いました。まずそうやって自分でも向き合ったからこそ、「一緒にやりましょう」「あなたの声が聞きたい」と素直に伝えられたんじゃないかと思います。
荒井:クリエイターやアーティストの人は、自分が表現した仕事で、考えていることや感じていることを(社会や人々に)返しているという意識があるだろうから、わざわざ言葉にしなくても、という人ももっといるかと思ったけど……。意外とみんな賛成してくれたんだね。
筒井:そうですね……。もっと断られるかもしれないと思っていたので、ありがたかったです。

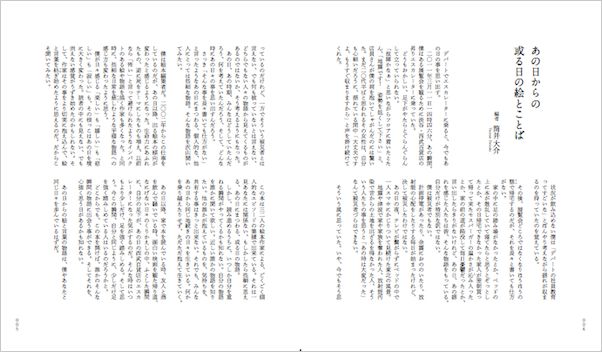
筒井大介さんが作家へ依頼するにあたり、書いて送った文が「まえがき」となった(『あの日からの或る日の絵とことば』より)
───荒井さんは、依頼を受けてどのように思われましたか。
荒井:絵本作家は文字も扱い、絵も扱いますから。何か大きな出来事が起きたとき、たとえば学者とか音楽家とか、いろんなジャンルの人たちの、いろんな記録性があると思うんですけど、「絵本作家の人たちがどう感じたか」という視点は、僕自身考えてもいなかった切り口で、新鮮な感じがしました。

───引き受けるどうか迷われた作家さんも、いらっしゃったのでしょうか。
筒井:デリケートなテーマだと思うので、逡巡された作家もいらっしゃったと思います。そもそもこのことについて自分が言うことがあるのかどうか、と。言う内容があるかではなく、どちらかというと「何かを言う資格があるのか」に近いですよね。被災している訳でもないのに……という逡巡はあったと思います。 依頼に対して、すぐに返事くださる方もいれば、数日お返事がなくて、「いかがですか」と伺ったら「自分が参加していいのかわからないけど、書いてみます」「何を描けるかまだわかりませんけど」という方もいました。
二つ返事で「よし、やりましょう」という方はほとんどいなかったです。「ああ、ついにこういう依頼が来てしまった」と思ったという方もいました。引き受けてくださったけど、「絵本作家のあの頃のことなんか、興味がある人がいるのか」と疑問を投げかけられたこともありました。このような理由でお願いしたいと思っているし、やる意義があると思いますとお伝えして、話し合って、納得してくださった方もいます。逆に、「ずっとひっかかっていたことに向き合う機会をもらった」と言ってくださった方もいます。
───ヨシタケシンスケさんの漫画の中の、「あー『当事者ポイント』が足りないですー」という言葉にはハッとさせられました。
筒井:僕も原稿を見たときは驚きました。まさに、ヨシタケシンスケさんがああいう言葉で言ってくれて、「そうか、このずっとある後ろめたさみたいなものは、まさに『当事者ポイント』の足りなさなんだ」と……。

ヨシタケシンスケさんの絵(『あの日からの或る日の絵とことば』より)
●食べ物の記憶、土地の記憶、続いていく不在
───本秀康さんは「おにぎりパーティ」と題した漫画を描いていますね。
筒井:あの頃、本秀康さんと絵本の仕事をしていたので、よくやりとりをしていました。本さんが「俺さー、ずっとおにぎりにぎってたんだよね」と言っていたことを覚えています。
加藤休ミさんに依頼をしたときは、「あんぱんと牛乳を描こうかなぁ……」と言っていました。地震の揺れを感じて、当時手伝っていた学童クラブに子どもたちの様子を見に行った帰りに、“あんぱんと牛乳”を無性に欲したそうです。

加藤休ミさんの絵(『あの日からの或る日の絵とことば』より)
───おにぎりもあんぱんも、いつまでこの状態が続くか分からないという不安の中の、腹ごしらえの心境を感じさせますね。加藤さんのエッセイの中でも「長期戦になるかもしれない」という表現がありましたが……とっさに食べ物のことを考えるのは生存本能なのかもしれませんね。
筒井:穂村弘さんは「あの日からしばらく、私は毎日何個も梅干しを食べていた」と書いてましたしね。

穂村弘さんのことば(『あの日からの或る日の絵とことば』より)
荒井:食べ物って、その日の感じとか、手ざわりみたいなものを思い出すきっかけになるよね。
───ヨシタケシンスケさんと本秀康さんは漫画も描いていて、穂村弘さんは歌人、原マスミさんはミュージシャン、本橋成一さんは写真家……。こうして見ると、一口に絵本作家といってもいろんなジャンルの方が参加されていますね。
筒井:幅広い視点が欲しかったので「絵本という共通項」はありつつ、なるべく様々な活動をしている作家たちに参加してほしかったんです。年齢も、若い世代はハダタカヒトさんや村上慧さん、阿部海太さん、上の世代はささめやゆきさんや本橋成一さん、飯野和好さんやスズキコージさんがいらっしゃいます。
1988年生まれの村上慧さんは絵本『家をせおって歩く かんぜん版』(福音館書店)を出版されていますが、もともとは現代美術の方で、自作した発泡スチロールの家を背負って歩き、人の家の軒先に置かせてもらったりしてそこに泊まる生活をされています。2014年からその「移住を生活する」プロジェクトをはじめたのも、2011年の震災がきっかけだったと聞いたことがあります。

村上慧さんの絵(『あの日からの或る日の絵とことば』より)
───村上さんは「住所は地面に割り当てられているもので、樹は地面から生えているものだ。だからその生えている樹は、その住所に生えていることになる」と考えます。「樹」と「住所」の関係性を考える視点がおもしろいですよね。
木と言えば、ハダタカヒトさんが描いたサルスベリの木と、木が切られたあとに思いを寄せた文も心に残りました。
そして坂本千明さんが、亡くなった友や両親や飼い猫の不在は自分が生きている限り永遠につづくのだから、錨は自分でおろすしかないと書いていたことにも胸を打たれました。














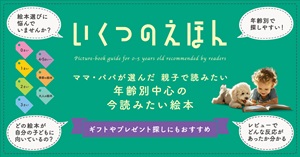
 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪ 

